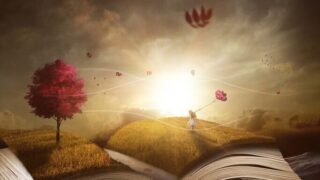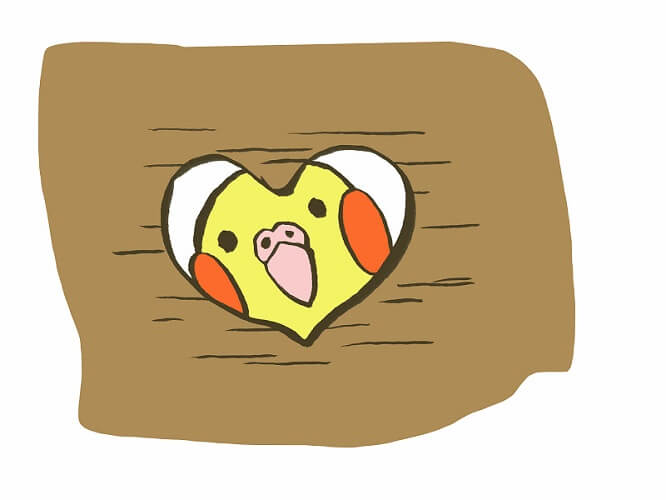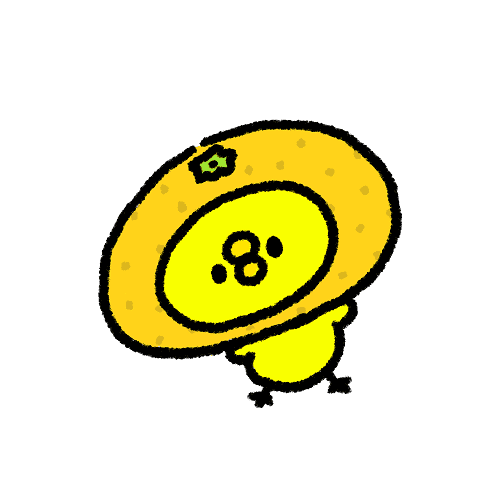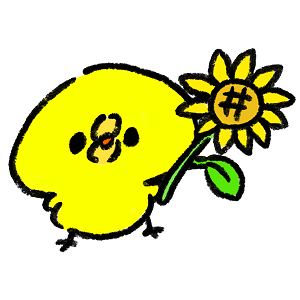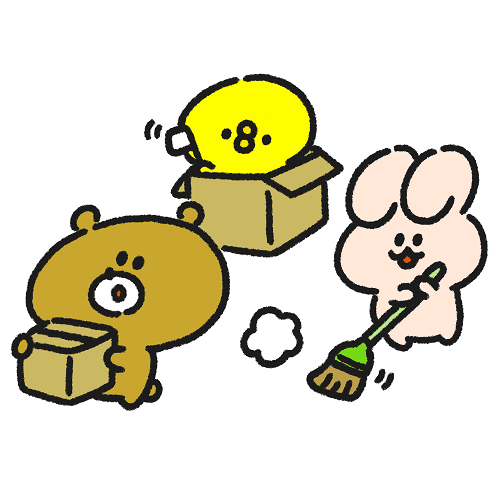インコの発情期行動と発情しすぎに注意!発情兆候3パターン

鳥が発情する条件は 日照時間が10時間以上 餌が豊富にある季節 育雛に適切な温度 育雛環境が整っている …などですが、飼い鳥は年間を通してこれらの条件が整っているため、年じゅう発情している個体が多いです。
特にオカメインコサイズ以下の小型・中型インコはその傾向が顕著です。
インコたちが見せる行動をよく観察すると、現在“絶賛発情中”かどうかがわかります。
インコの発情期は飼い主への「おねだり」「おさそい」行動

飼い主を自分のパートナーと見なしているインコの発情相手は飼い主です。
発情モード全開のインコは、飼い主に向かって「おさそい」行動に出ます。
いわゆる「シャチホコポーズ」とかですね。
「吐き戻し」の餌をパートナーにプレゼント。
オスはおしりスリスリ。メスは尾羽を上げる。

セキセイインコのメス
雄でもやることがあります。この動画では雌雄は分かりにくいですね。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 13, 2022
インコのパートナーが飼い主であれ、同居の鳥であれ、繁殖を望まないのであれば、発情はインコの心身に余計な負担をかける行為です。
飼い主に対するインコからのお誘い行動が見られたら、さーっとケージに戻すなどの行動の抑制が必要です。
また普段からインコに性的刺激を与えないことも大切です。
インコのくちばしは性感帯なので触らないこと。くちばしを指でさわると、インコが発情モードに入ることがあります。
頭や耳の周りをカキカキしてあげる程度ならいいですが、背中や体の方をさわるのも性的刺激になるので控えましょう。
インコの発情期に巣作り行動に奔走する

インコの繁殖を行うとき以外は、ケージに巣箱や巣箱に見立てられるものを入れてはいけません。
冬の防寒目的で巣箱を入れる人がたまにいますが、それは間違いです。
またインコは鳥種によってさまざまな巣作り行動をしますので、飼っているインコの特徴を知っておくことも大切です。
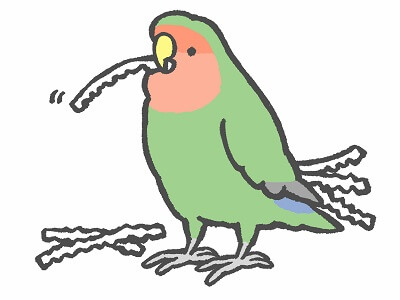
例えばコザクラインコは紙を細長くちぎって翼に差し込んで運び、巣作りをしようとします。
野生下のコザクラインコは小枝などを拾ってうろ(樹木の穴)に運んで巣作りをするのですが、飼育下では小枝がないので 代わりに紙を小枝のように細長くちぎって代用するのです。
以前に紙を取りあげられたコザクラインコが自分の羽を抜いて齧り、それを自分の腰に刺すことを始めたことがありました。意識は自分ではなく、なるべく外に向かせることが退屈の対処であり毛引きの改善法です。それは人や鳥とのコミュニケーション、フォージング、チュワブルトーイ、紙などになります。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 1, 2021
このツイート にあるように、コザクラインコの紙かじりを取り上げたら毛引き等の問題行動に走る例もあるとのこと。
巣作り行動は本能や習性によるものなので、巣作りをやめさせたり巣材を取り上げるだけで解決するものではありません。
おもちゃやフォージングをうまく利用して、インコの気を引く別の解決策を模索するのが最善でしょう。
実際にフォージングは発情抑制対策のひとつとして有効です。
コザクラインコのオス
スリスリ始める前でしたら、気を逸らすタイミングとしてはよいのではないかと思います。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 6, 2022

オカメインコの場合は、放鳥時に箱など中に籠れる場所を探して入り口をかじったり、ケージの中では底の敷き紙をかじったり浮かせて空間を作ったりして、巣をこしらえようとするそぶりを見せます。
インコの発情期には縄張り意識から敵意をむき出しにすることもある

特にオスのインコは発情期に攻撃的になる事が多く、それは強い縄張り意識が原因です。
ケージに近寄っただけでインコがかみついてきた…などの場合は、このケースが多いでしょう。
このように行動が大きく変わるのは発情でホルモンバランスが崩れていることによるところが大きいので、インコを叱りつけたところで改善されるはずはありません。
飼い主の方が「そういうもの」と受け止めて、嵐が過ぎ去るまで待ちましょう。
インコの発情期が去ると次はどうなる?

アクセルを踏む強さはエストロゲンの量や体質、環境によります。発情を止めるのはエンジンを切ることです。それには燃料を減らすこと、つまり食事制限となるのです。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 5, 2021
昨年その状況になりビックリしました。何もない床を温め、自分の足を生まれてもいない子供に見立ててご飯を吐き戻してあげていていました。落ち着くまでに1ヶ月以上でした。食欲は旺盛で元気があったので先生からそこまで心配はいらないといわれましたが…心配でした。
— れぴまる (@repimaru_m_m) September 22, 2021
先生、まさしく10日前に発情期が終わらぬ前に換羽に入り、しんどかったのか、14日は一日中寝ていて、食欲が それから落ち、MAX116gあった体重が10日で98gになりました。
ようやく今週から活発になり始めましたが、まだ食欲は イマイチです。けれどまぁまぁ元気なので
餌に— 穏龍 美月(龍のなみだ) (@mizukionnruu20) September 22, 2021
インコが発情しすぎるとどうなる?発情抑制のやり方は?

発情は本能によるもので意図的に止めることはできません。
生き物が子孫を残そうとするのはごく自然で当たり前のことです。
しかしインコが年がら年じゅう発情している様子が見られるなら、それは鳥体にとって不自然かつ不健康である証拠。
どこかで飼育方法が間違っていることを意味します(とはいえ、完璧にインコの発情を制御することはできません)

食餌制限をがんばっても、どうにも過発情が止まらない場合は、メスならホルモン剤の投与で発情抑制ができます。
オスは食事制限と運動で発情抑制効果が期待できますが、それらをがんばっても抑制効果の確実性はありません。もちろん健康的なことではありますが。
雄の発情によるスリスリで射精に至ることは普通にあります。射精回数が多くても大丈夫かは分かっていませんが不自然に多くならない方がよいのではないかと思います。何度も擦りつけることにより総排泄腔粘膜が傷ついて出血することもあります。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 4, 2022
オカメインコの研究では、雌雄共にプロラクチンが発情を抑えることが分かっています。プロラクチンの分泌の始まりは卵の存在です。偽卵を置いて見せることで、オスの発情抑制に繋がる可能性はありますが、まだ詳しいデータはありません。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 4, 2022
セキセイインコのオス
鳴管筋は男性ホルモンの影響で発達することが分かっておりこのために雄の方がおしゃべりが上手な仔が多いのです。発情が強いと鳴管筋が大きく発達し、咳や呼吸音が出ることがあります。雄の発情抑制は、今の所食事を1日に必要な分だけ与えるやり方をするしかありませんが、完全に止めるのは困難です。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) April 25, 2022
オスは定期的に動物病院で健診を受けて、精巣の発達や腫瘍、その他の異常を調べてもらいましょう。
セキセイインコのオス
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) May 3, 2022
インコの発情しすぎは寿命を縮める行為。飼い主さんが発情抑制対策を講じることが大切です。
ヨウムのメス
こちらは22歳のヨウムの雌です。動脈硬化による石灰化(赤矢印)が見られます。動脈硬化のリスク因子に高脂血症と高血圧があります。雌は発情すると血中の中性脂肪のみならずタンパクとカルシウムが上昇してドロドロ血液となって血圧が上がります。黄矢印は発達した卵胞です。発情抑制は大切なのです。 pic.twitter.com/RoFp8xZFXb
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) December 5, 2021
コザクラインコのメス
雌のコザクラインコの両第3趾の爪に見られた出血斑です。血液検査をした所、発情性の高中性脂肪症がありました。肝機能に問題はありませんでした。慢性的に発情している雌には爪や嘴の出血斑や変形、羽毛の変色や変形といったケラチン形成異常からくる症状が出ることがあります。 pic.twitter.com/cQXEo7jXgq
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) February 25, 2022
発情で高中性脂肪血症を起こすのは雌だけです。雄の発情ではならないです。肥満が原因の場合は、雌雄共になります。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) February 26, 2022
食べ過ぎ、高脂肪食、運動不足、甲状腺機能低下症などが原因となります。
血液検査をすれば発情性かどうかを鑑別できます。— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) February 26, 2022
老齢や運動不足で代謝が下がっていると、痩せていても高中性脂肪血症のことはあります。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) February 26, 2022
インコの発情抑制の基本は食事制限と運動です。フォージングも効果があります。
人では太るほど食べてしまうことを過食性障害と言います。その原因の多くはストレスと言われています。ではたくさん食べてしまう鳥は何が原因なのか?1つ目は発情です。発情すると雌は卵を産むためにたくさん食べ、発情吐出をする種の雄は、雌に餌を与えるためにたくさん食べます。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 18, 2022
そのため「肥満→食事制限」だけをすればよいのではなく、ストレスを他の方法で解消する必要があります。最も効果的なのは、運動です。その他フォージング、おもちゃや齧り木などのエンリッチメント、トレーニングなどで退屈を解消することも合わせて行いましょう。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 18, 2022