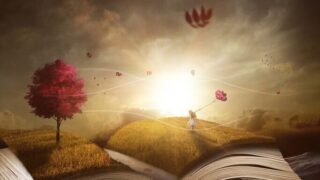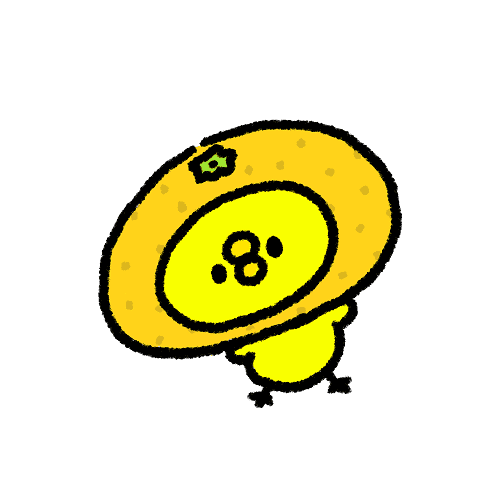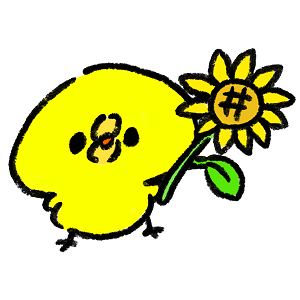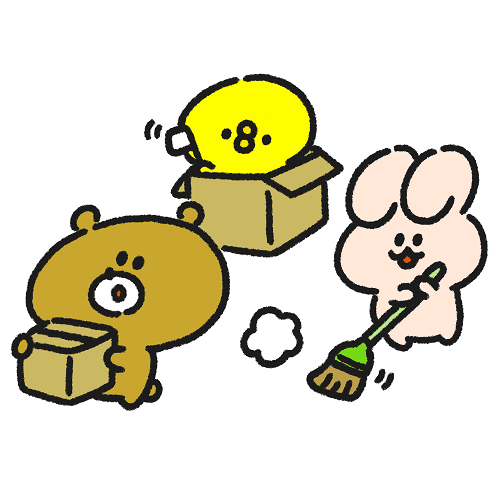インコの反抗期の接し方と性成熟期の問題行動への向き合い方

見た目がかわいいと、いつまでも「小さな子ども」扱いしてしまいがちですが、インコはどんどん大人になっていっています。
…とライフステージが変わるにつれ その精神状態やヒトに対する反応にも変化があるのが当然ですが、それを認識することなくインコを「永遠の2歳児」と見なしている飼い主が多いです。
インコの反抗期は2回ある【シーズン1】【シーズン2】

手乗り雛は 早いうちから親兄弟と引き離されている単羽飼いがほとんど。
インコのメンタルに多かれ少なかれ「分離不安」が植え付けられている飼育下のインコは、基本的な成長過程をたどらない場合が多いです。
それは幼鳥がお手本とみなすモデルがヒトだから。

ヒナのうちは成長の流れが遅かったり早かったり 時に不健全なこともあるため、こころの成長の個体差も大きいです。
そんなインコの反抗期は2回訪れます。
第一次反抗期・第二次反抗期、ともに順調な心の成長の証です。
インコの反抗期はどのくらい?いつから始まるいつ終わる?

相手が子どもであれインコであれ、反抗期の相手からはイラっとさせられることはしばしばありますが、反抗期は当たり前に起こる健全な成長の証と捉えることです。
第一次反抗期…インコに自我が芽生える時

べったりと飼い主に依存していた幼鳥が「自分は親とは別の生き物だ」をそこはかとなく自覚し始めるころに訪れる最初の反抗期です。
オカメインコの場合は特に個体差がとても大きく、2ヶ月齢から6ヶ月齢位の時期に第一次反抗期があります。
第二次反抗期…インコの思春期

ヒトと同じで性的な成熟期を迎えて、こころとからだのバランスを崩す不安定なとき。
甘えたいけど干渉されたくない、独立したい…といった相反する感情が入り混じって、当人(鳥)がますます混乱して精神的に荒れる時期です。
オカメインコの場合は、おおむね10ヶ月齢から1歳半くらいのころです。
インコの反抗期の接し方 3つのポイント

インコに必ず訪れる2回の反抗期と性成熟期の問題行動…
飼い主がこれらを事前に理解していないとショックを受けることもありますが、そんなときでも飼い主はインコへの接し方に一貫性を持ってください。

インコに噛まれた、威嚇された、あんなに穏やかだった子がどうして攻撃的に!?と思ったら、インコの発達段階(後述)をよく考えてみましょう。それは反抗期のサインかもしれません。
インコの問題行動が見られたら、原因が反抗期であれそれ以外であれ、飼い主は過剰反応しないことです。放鳥時であれば静かにケージに戻します。あくまで冷静に、インコに飼い主がひるんだりうろたえた姿を見せないことが大切です。
それが反抗期真っ盛りだったとしても、さっきまで怒っていたインコの方から「カキカキして」などと甘えてくることはよくあります。そんなときはインコのきもちをそのまま受け入れて甘えさせてあげてください。噛まれたことを根に持ってシカトしてはいけません。
インコの反抗期の先に性成熟期・発情期あり【シーズン3】

飼育下のインコは野生と違って1年じゅう発情を繰り返していることが珍しくありません。
発情するとホルモン分泌によりちょっとしたことでも興奮したり、パートナーがいれば攻撃的になったり、縄張り意識が強くなって、飼い主に対しても敵対心をむき出しにします。
オカメインコの性成熟期は1歳半~6歳頃

オカメインコの場合は、1歳半から6歳くらいまでが性成熟期でそれに伴う問題行動が目立つ時期ですが、7歳~10歳くらいまでは問題行動が起こる確率は高いと思っていてください。

オカメインコのは7歳以降は数字だけを見ると「繁殖引退期」ですが、メスは10歳で産卵する子もいますし、性成熟期よりは精神的に安定した時期とはいえ10歳くらいまでは問題行動が多いものです。
そういうものと割り切って問題行動にキレたりせずに、温かい目でインコに接してください。
問題行動の根本原因は「発情」であることが多い

ふだんおとなしいインコが攻撃的になった場合は、根本原因は「発情」であることが多いです。
その原因を分析し、問題行動が目立つようであれば、その日付や状況についての記録を付けておくことをおすすめします。

過剰産卵や巣ごもり行動などが多く見られるなら、飼い主が発情抑制対策を講じる必要があります。
インコの問題行動の原因には多かれ少なかれ「発情」が一枚かんでいますので飼い主がインコのこころに寄り添うと同時に発情抑制対策を継続することが重要です。