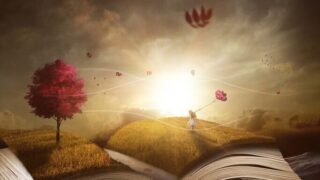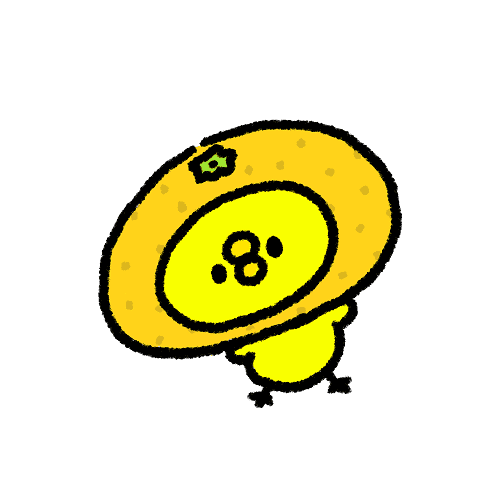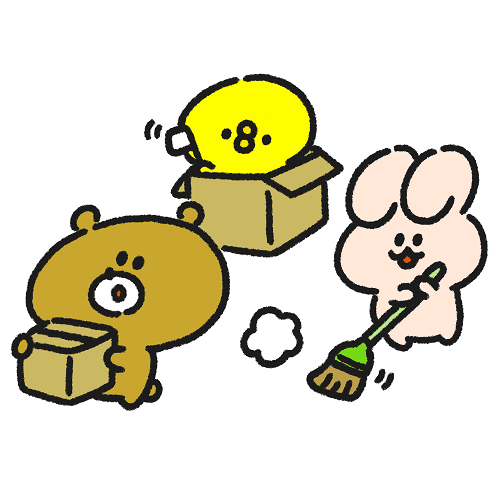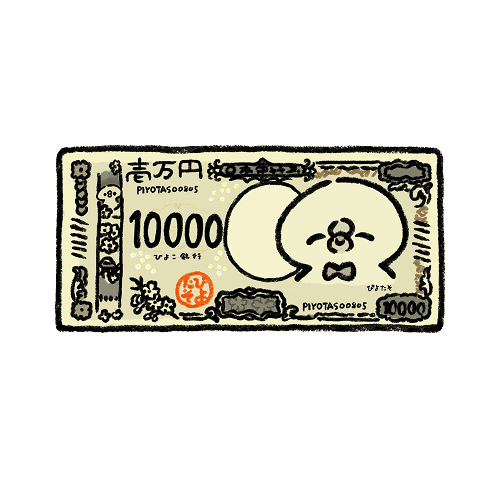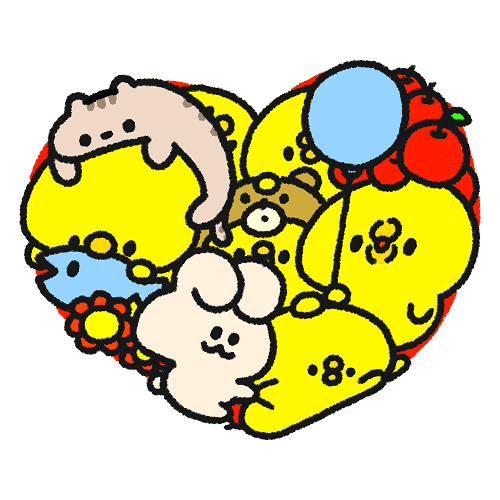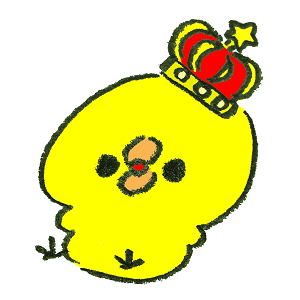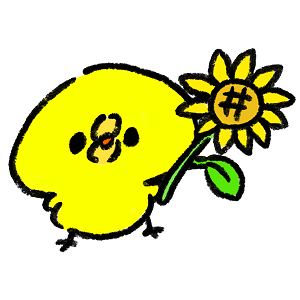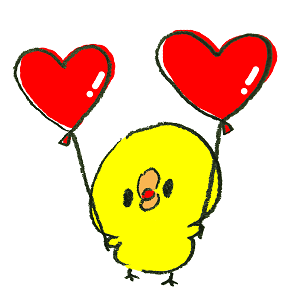ペットロスは鳥が一番きついとマツコが言ったのはなぜか?

マツコの番組で鳥のペットロスが一番きついって言ってた 鳥だと一番会話らしいコミュニケーションが取れるからだそうな
— ウメズ (@umezu_bot) February 27, 2016
「ペットロスは鳥が1番キツイ」#マツコ会議
— ❈vanilla❈地味鳥園 (@vanilla_crow) February 27, 2016
ペットロスで鳥が一番きつい理由は「鳥は人に恋をする」から

一説では「ペットロス」がもっとも強く起こるのは犬・猫の飼い主ではないとのこと。
ペットロスは鳥の飼い主がいちばんきついと言われることがあります。
被食者の小鳥は 性質が臆病ではあるもののひとたび飼い主との愛情が結びつくと、それはとても強固なものになります。

鳥は想像以上に愛情深い生き物。鳥は人に恋をする。この点が犬や猫は全く違うところです。
犬や猫も人と仲良くなれますが、人に恋をすることはありません。
特に犬は飼い主も「群れの一員」とみなす習性があります。
あまり良くない表現ですが・・・飼い犬から『なめられている』飼い主は犬自身から「格下」に認定されています。
それにより人間社会でいえばパワハラやモラハラのような態度を飼い犬が飼い主にとるケースが多いです。
飼い主が手に負えない「問題犬」です。
手乗りの小鳥たちは飼い主に全身全霊で愛情をぶつけてくる!

その一方で、鳥は小さな体にはちきれんばかりの愛情を詰め込んで、飼い主と過ごす至福の時間に
全身全霊で愛情をぶつけてくる生き物です。
だからそんな天使を失った飼い主のショックは計り知れないくらい大きいものです。
文字通り「心にぽっかり穴があく」感覚そのもの。精神的にかなりきついものがあります。
ペットロスは鳥が一番きつい!と言われる理由はここにあると思います。

私が生まれて初めてペットロスの強烈な喪失感を味わったのは15歳の時です。
小学2年生から大切に育ててきた手乗り文鳥が7歳で寿命を終えたときでした。
ちょうど思春期まっただ中ということもあって「胸にぽっかり穴があく」感覚と「大切なものを失った」喪失感をあれからうん十年経った今でも忘れません。
広告
「鳥はしゃべるからペットロスの喪失感が大きい」は半分は間違い

マツコ会議の番組中では
…というようなことを言ってましたが、鳥が会話らしいコミュニケーションが取れるから…というのはちょっと違うと私は考えています。
飼い主が一方的に話しかけてコミュニケーションをとるのは犬や猫でも同じことであり、文鳥などのフィンチはさえずりはしますがしゃべりません。

そもそもインコやオウム類くらいしかおしゃべりはしませんし、基本的に歌ったりしゃべったりするのはオスのみです。
メスでもしゃべる個体が全然いないわけではなくて、簡単な言葉をしゃべる仔もたまにいますけれど、メスは静かな子が多いです。
10歳過ぎてから新しい言葉を覚えたオカメインコの話

余談ですが、うちの12歳オスのオカメインコのおーちゃんは10歳で連れ合いを亡くしてから再び私にべったりになり、シニアなのに幼鳥のように新しい言葉や歌を5個以上覚えました。
私がカキカキしてあげてるときに何度も「きもちいーね♪」と話しかけていたら、「きもちいーね♪」が十八番(おはこ)となりました。

ご機嫌な時に聞いた言葉は、特に簡単に覚えてしまいますが、10歳という年齢を考え合わせると、これはすごいことだと思います。
鳥類の記憶には臨界期があると言われていて、若鳥の頃に覚えた歌や言葉をずっと繰り返し発しているのが普通のことなので・・・
オカメインコの平均寿命の折り返し地点を過ぎたところで、シニアオカメが新しい言葉を覚えるなんて思っていなかった展開でした。
インコは最愛のパートナーを求める生きもの

手乗りオカメインコのおーちゃんはパートナーができてからは彼女一筋で、私との距離は少し開いていました。
しかし連れ合いを失ったことでその対象が再び私に変わった時から私の言葉に一生懸命耳を傾けて、新しいおしゃべりを覚えていったのです。
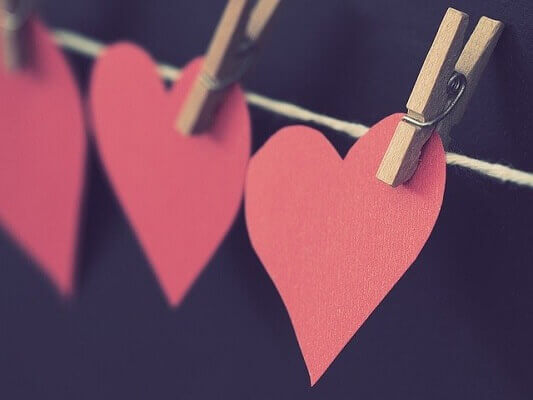
「鳥頭」なんて嫌味な言葉があるものの鳥は想像している以上に賢い生き物ですが、加齢と共におしゃべりが少なくなっていくもの。
繁殖行動最盛期はよく鳴いたり歌ったりしゃべったりしますが、加齢とともに静かになっていくことが多いです。
しかも鳥のさえずりやおしゃべりは彼らのコミュニケーションツールですから、コミュニケートする相手や対象がなければ、年がら年中一人でしゃべってるわけでもない。
だから鳥のペットロスにおける「喪失感」はおしゃべりや歌を歌うコミュニケーションの有無よりも「情」が大きく絡んでるはずです。
広告
鳥のペットロスのきつさは「恋人」への愛情の深さから来ている

鳥は飼い主を「恋人」とみなし、そして飼い主も同様の感情を抱いたとき、愛鳥を亡くした喪失感は
言葉では言い表せないほどきついものになってしまうのでしょう。
人は鳥を家族や子供と捉えがちですが、鳥からすると人を恋人や友達のように捉えているのではないかと思います。
何をしてあげたいかよりもまず先に鳥たちは何をして欲しいのかを感じてみると新たな発見があるかもしれません。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) August 16, 2022
そこからどうしようもなくペットロスに陥ってしまい、立ち直れない抑うつ状態が長く続くことで本物のうつ病に移行することも珍しくありません。

ペットロスを「ロス」とか簡単に言いますけど、「ペットロス症候群」は一種のメンタルの病気です。
精神を病むのですから、甘く考えてはいけません。
犬・猫のような「比較的」大きなペットを飼っている人から見たら
…と思う人も多くいますよね。
私も過去に、面と向かってそう言われたことがありますが、ペットロスの悲しみの深さに動物の種類は関係ありませんよ。
ネコいぬワイドショーで、眞鍋かをりが、迷子鳥を探している人のチラシを指指して半笑いでディスっていた。
犬猫以外の飼い主は小馬鹿にされる番組。非常に不愉快。迷子鳥が家に帰れますように。#ネコいぬワイドショー#迷子鳥 pic.twitter.com/CXif4LiZpZ
— mousugunakanji (@tibiccono) May 6, 2023
真鍋かをり BS朝日『ネコいぬワイドショー』で「迷子の鳥を探してます」飼い主のチラシを嘲笑して炎上、「犬猫以外は家族じゃない」愛犬家の“上から”意識か
「“鳥探してます”の場合、無理じゃ〜ん?って思うのよ。特徴とか、名前とか書いてあるんだけど、いや〜、無理だと思うよ〜みたいな」5月5日放送のバラエティー番組『ネコいぬワイドショー』(BS朝日)にゲスト出演した眞鍋かをりが、街中で見かける“迷い鳥”を探すチラシについて述べた私見。
手で口元を押さえつつも堪えきれず、笑いながら話す眞鍋に同調するように「鳥はさ、確かにね」と爆笑する、番組コメンテーターの『さらば青春の光』森田哲矢と周囲のスタッフ。片や、そのやりとりを不安そうに苦笑いを浮かべる司会のフリーアナ・森千晴の様子が放送された。
この飼い主の切実な思いを踏みにじるかのような発言に、ネット上で批判の声が上がると、一部のネットニュースが記事配信したことで瞬く間に拡散されて炎上騒動となったわけだ。
番組自体は犬や猫のペットを飼うゲストのエピソードトークなども掘り下げる動物バラエティーだ。そんなほのぼの番組だけに、また自身も愛犬家として登場した眞鍋だけに余計に目立つひと言に。見逃し配信サービス『TVer』では、炎上騒動を受けてか、まもなく配信期間を待たずに打ち切られた。
via:週刊女性PRIME
愛する家族を失った喪失感と悲しみは計り知れないものです。
つらい飼い主の心を浄化するペットロスカウンセリングは必要

ペットロスはペットに対する罪悪感や、生前にもっとやってあげられることがあったのでは…と考えてしまう後悔の念から来ていることが多いです。
ペットの魂を案ずる気持ちなども交錯して悲しみの連鎖は複雑に絡み合っています。
ペットロスは落ち込みではなく心の病気です
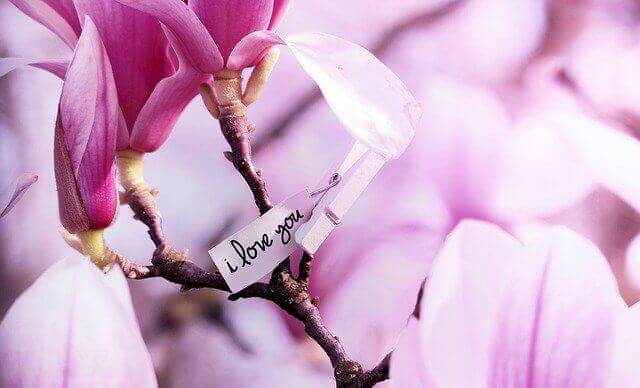
ペットの死により睡眠障害や摂食障害、抑うつ状態に陥って、メンタルクリニックを受診する飼い主も後を絶ちません。
ペットロスが重い人ほど新しいペットを迎えることの罪悪感が強かったり、気晴らしや気分転換ができずにふさぎ込んでしまったりします。
そんなペットロスで苦しんでいる飼い主の立ち直りの良いきっかけのためにお勧めしたいのが、心理カウンセリングです。
心理カウンセリングは他力本願ではなく自力本願

心理カウンセリングというと「話を聴いてもらう」だけだと思っていませんか?
確かにそういう側面もありますが、それはカウンセリングの本質ではありません。
つらさMAXであるペットロス初期には、心の中の思いをすべて吐き出すことが「心の浄化」につながります。
そこから先はつらさの具体的な原因や出来事の整理を行い、どんな行動や考え方をすればいいかをカウンセラーと一緒に探していくことで、ペットロスから立ち直るまでの時間がぐんと短縮されるのです。
広告
ペットロスへの向き合い方!自分のこころを救えるのは自分だけ

人から「教わる」ではなく自分で「気づく」ことがもっとも重要で、腑に落ちないとペットロスから
なかなか解放されません。
自分を救えるのは自分だけです。プロのカウンセラーはそのお手伝いをする黒子です。
おおむね3か月以内にペットロスから立ち直れれば、メンタルの外傷は最小限で抑えられますが、長引くほど辛さから解放されづらくなります。
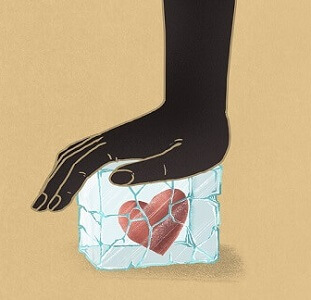
人の心は想像以上にきゃしゃで壊れやすいものなので、目に見えないのに、あっという間に
心の傷が無意識下で重症化して「抑うつ」が本物の「うつ」になります。
ペットロスが長引くほど、自力のみで立ち上がるのが難しくなるだけではなく、我慢を重ねると
確実にメンタルが崩壊します。
こころを救うツール(他人)をうまく利用して早期に立ち直る

日本では欧米のようにこころのケアに重点を置かない風潮があるから、日本人にはうつ病も自〇も多いのです。
どんなに美辞麗句を並べられても、本心から心配してくれたとしても、他人が他人を救うことはできません。
自分のこころを救えるのは自分だけ。
言い方がアレですが、他力(=他人)はツールのひとつでしかありません。
1日でも早くペットロスから回復するために「心理カウンセリング」というツールとマンパワーを活用することも立ち直りのために有効なひとつの方法です。
カウンセリングといっても対面ではなく、スマホからのオンラインカウンセリングサービスもあるので、鳥のペットロスで辛い思いをしている方は一度利用してみるのもいいと思います。
ペットロスが苦しすぎるならペットの気持ち鑑定がおすすめ


ペット霊視の鑑定師
愛猫にとって幸せな日々だったわかったのでホッとしました。まだ涙が出る毎日ですが、優瓜先生の霊視が心の支えになりました。お気に入りだったウェットフードとおやつを食べたがっているとのことでお供えしたのですが「食べてね」と声を掛けたら、ロウソクの炎がゆらゆら揺れながら大きく縦にボーっと伸びてびっくりしましたが怖くありませんでした。きっと喜んでくれたのでしょう。
「仏壇にいい匂いがするものをお供えしてと言ってるけど?これは何だろう?柔軟剤のにおいみたいな…」との優瓜先生の言葉に笑いました。うちの子は取り入れた洗濯物にダイブするのが好きだったのです。これを聞いたので49日まで仏壇の部屋に洗濯物を取り入れることにしました。あの子が生まれ変わるかもしれない頃に、また優瓜先生の鑑定をお願います。
インコのメール鑑定を優瓜先生お願いしましたが「羽根を身に着けて」とのメッセージに驚きました。羽を使ったアクセサリーを作っている最中だったんです。同じ思いでいてくれることがわかり、涙が出ました。
寝たきりで1年間辛い日々を送っていた愛犬の本音も教えてもらえて涙が出ました。優瓜先生が「わんちゃんが甘い水を欲しがってるんだけど?」とおっしゃられてびっくり。寝たきりの間、リンゴの絞り汁を飲ませていたのです。リンゴを買ってきてすぐにお供えしました。苦しい気持ちがすっきりしてきて、本当に良かったです。
via:優瓜先生の口コミ
年末に亡くなったペットの鳥さんについて春清先生に鑑定していただきました。母が保温をしてくれたことや、あの子が私の肩に乗るのが好きなこと、妹が遊び相手であったこと…全てお伝えしていないのに先生はお見通しで驚きでした。本当に、あの子の気持ちを聞いて伝えていただいてるのだなと思いました。
春清先生に亡くなったインコの事で視てもらいました。もう1年前でしたが、早すぎた突然の別れに中々消化出来ず、苦しい日々でした。何度も先生のメ-ルを読み返し涙し、やっと受け入れられそうです。先生とあの子の会話に励まされ、あの子らしいところもあり、あの子がよく私の事見ていたなと嬉しかったです。
春清先生にうちのペットのインコのことをメール鑑定していただきました。うちの子自身の事はもちろん当たってたのですが、それに加えて私達人間の事も全て当たっていて驚きました。質問にも書かなかったのだから、本当にうちの子からしか読み取れない内容なのに…。
春清先生に愛犬についてメール鑑定していただいた者です。あまりに内容が濃く、しかもはっきりしており、本当に視えている方だと驚きました。「規則正しい生活の中…」とありましたが、まさにその通り過ぎて言葉が出ませんでした。朝と夜2回、きっかり定時にご飯をもらえていたのは確かです。私へのメッセージの中にある「ずっとずっと大好きだよ」は、毎日あの子の写真に言い続けていたメッセージとまったく同じで、またビックリです。悲しみから救ってもらいました。読み終わってから放心状態となってしまいました。
春清先生に愛犬の気持ちを視て頂きました。何が気に入らなくてイライラしているんだろう…ずっと考えていました。まさか名前だなんて(笑)母から譲り受けた子だったので、改名は考えていなかったのですが。名前を途中で変えて本人は理解できるのか?そんな思いで、本人が望む名前を教わって呼んでみたらまさかの反応!!凄い喜んだ顔でとんできて、しつこいくらい舐めまくり、ヒステリーが治り穏やかに。こんな事あるの!?と主人と大笑いしました。
引用元:春清(かすが)先生の口コミ
とても愛していたペットのインコが急に亡くなり、毎日が辛い日々でしたが、のあか先生に今のあの子の事聞き、なんとか立直り、最近鳥の専門店に出かけたりして希望が出て来ました。あの子からのメッセージをヒントに探します。
亡くなった父の気持ちをどうしてもしりたくて、故人対話の項目があったのあか先生にお願いしました。何年も、いえそれ以前からほとんど会話することなく本音を聞くこともなく過ごしてきたので、亡くなってから気づいたことによりとても心が苦しくいましたが、鑑定結果を読んで涙がとまりませんでした。すぐに気持ちの切り替えとは難しいですが、伝えて頂いた言葉を心にとめ進んでいきたいなと思いました。故人のことで立ち止まっている方がいるならのあか先生をオススメしたいです。
亡くなった大切な子達の今の現状を知れて良かったです。今月に亡くなった愛犬がまだそばにいてくれて私には声は聞こえないですが、のあか先生を通じて気持ちを伝えてきてくれたこと、世界一あなたのことを愛していることは一生変わらないし、幸せな人生をありがとうって今は思えるようになりました。先月に亡くなった愛犬のこともみてもらい、先生に話してもいないのに亡くなる状況のこともピタリとあてて本当にすごいと思いましたし、私を選んで来てくれたことが本当にすごく嬉しかったです。
亡くなった愛犬についてのあか先生鑑定して頂きました。あまり頂けないような新鮮なメッセージを頂き少し驚きましたが、逆に想像していなかったお言葉を頂いた事で視てらっしゃるんだろうなぁと感じることが出来ました。動物に接してらっしゃる先生ならではと言うべきか…。嬉しい驚きでした。四十九日過ぎ落ち着きましたら是非又お願いしたいと思います。
引用元:のあか先生の口コミ
.