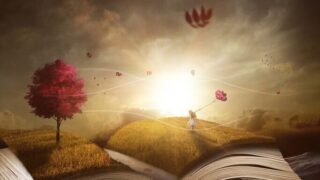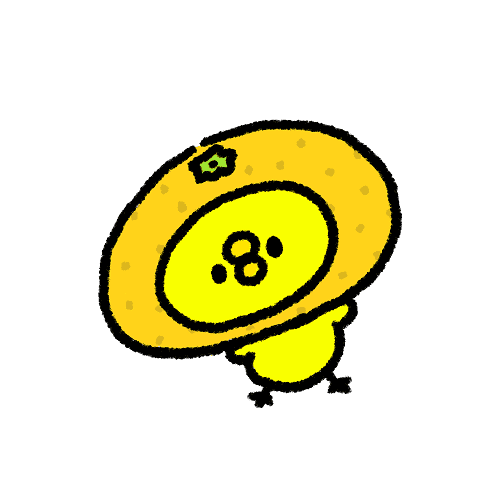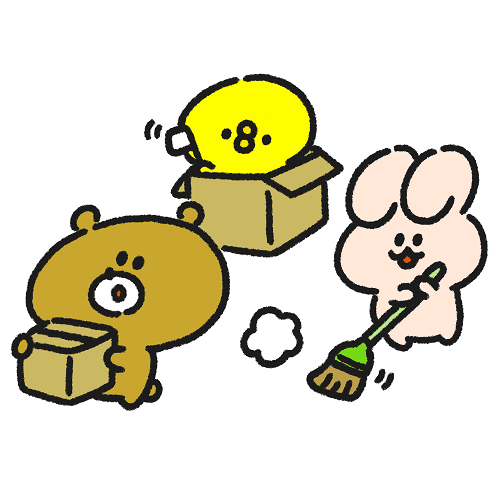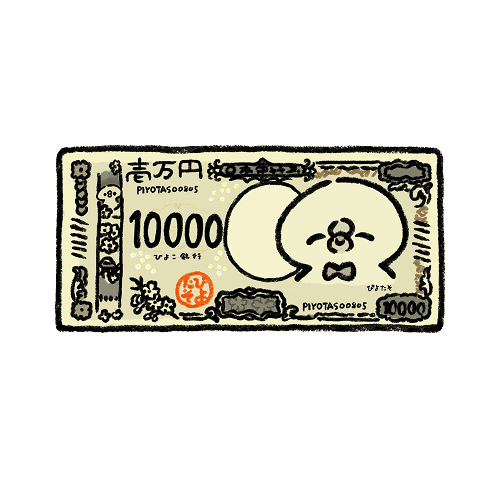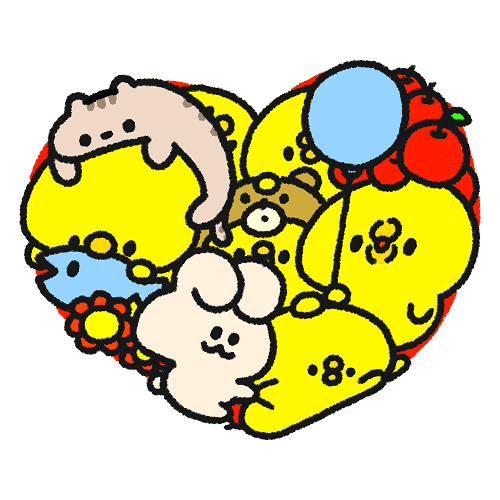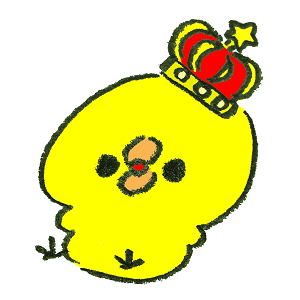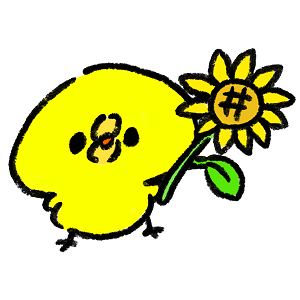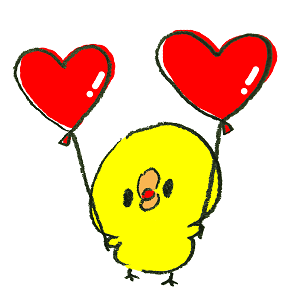セキセイインコの飼い主の寄稿です
私のセキセイインコ(すずめ)は
現在5歳のメスです。
インコを飼うのが初めてで
知識も準備も足りておらず、
基本的には自由に過ごさせ、
甘やかして育てていました。
セキセイインコの卵管脱緊急手術で発情抑制を決意した体験談

画像はイメージです
最初の異変は、
すずめが1歳になった頃。
見たことのない表情と
ポーズで固まっていたのです。
シャチホコポーズと呼ばれるそれは
インコの発情のサインで、
すずめは初産卵で6個を産みました。
その後もすずめは年間通して
発情と産卵を繰り返しました。
セキセイインコが1歳でシャチホコポーズ!過剰産卵を繰り返すようになって

次第に産む卵の数が
10個前後に増えていき、
心配になった私は
動物病院に相談しました。
過発情・過剰産卵の予防として
獣医からアドバイスされたことは、
発情対象を近づけないこと
適度なストレスを与えること
…でした。

セキセイインコの発情対象は
人であったり物であったり
色々です。
私のセキセイインコの発情対象は
私だったので、
発情の兆候がみられたら
家族にお世話を変わってもらうことにしました。
これは発情の兆候がみられてからの対処でも遅くない
と獣医から言われましたが、
すずめは気性が荒くて
私以外の人間には攻撃的なので、
我が家ではその方法では
うまくいきませんでした。

適度なストレスとは、具体的には
食事制限、ケージ内の模様替えや
移動でした。
安心して産卵できる、
落ち着く環境を作らないことで
発情が抑えられるというので
自分の力だけでできる
こちらの対策を
進めることにしました。

食事制限については
それまで全くしておらず、
インコの体重も
把握していませんでした。
発情させないためには
少し空腹くらいでいるのがいい
とのこと。

すずめは平均より重めの
42グラムだったので、
獣医の指導の元、
セキセイインコの平均体重である
30グラム代まで体重を落とすことを
目標にしました。
餌を餌箱に入れたままにせず、
朝と夕方に時間を決めて
与えることから始め、
毎朝の体重測定や
ケージ内の模様替えも
同時に行いました。
長生きを選ぶか自由を選ぶか?究極の選択を迫られたが…

セキセイインコの飼育法を
変えてみたものの、
すぐには体重も変わらなければ
発情も抑制できず、
獣医からぴしゃりと言われました。

このときはまだ
過発情・過剰産卵を抑えるために
ストレスのある生活を送らせることに
私の中には罪悪感と迷いがありました。
獣医はそれを見抜いていたのだと
思います。
セキセイインコの卵管脱を目の当たりにして卒倒し…【閲覧注意】
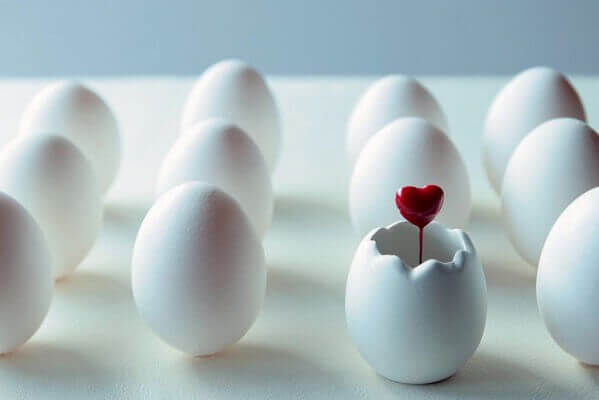
インコにストレスを与えることに対する
罪悪感をなかなかぬぐえなかった私は
どうしても強硬な対策は取れず、
中途半端なことを続けていました。
そんな私の意識が大きく変わったのは、
すずめが卵管脱になってしまってからでした。
お尻から赤いものが出ている場合は、卵管脱、クロアカ脱、クロアカ腫瘍などがあります。単純な卵管脱は、卵管口が緩んで、卵管が反転して脱出したものですが、卵管重積を起こすこともあります。卵管重積は卵管の途中から重積を起こしてお尻から出てくるものです。この場合は、緊急手術が必要です。 pic.twitter.com/WCU0eoYQSa
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) June 24, 2020
雌の鳥のお尻から赤い物が出ている場合は、クロアカ脱、卵管脱、ポリープなどがあります。画像はブンチョウのお尻から出てきたポリープです。治療は茎を結紮して切除しますが再発することも多いです。慢性発情が原因と見られています。下血や排便し難い場合は、ポリープができていることがあります。 pic.twitter.com/to6f5W2LmS
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) September 27, 2020
ケージ周りの環境を変えたことで
発情期がやってくるペースは
ほんの少し落ちたものの、
過発情と過剰産卵が続いたことで
卵管に炎症が残っていたことから
すずめのおしりから卵管が
飛び出てきてしまったのです。
深夜に飛び出た卵管を見て卒倒してしまい…

卵管脱になっても、すずめ自身に
衰弱している様子では見られませんでした。
しかし臓器が出てきたのを見て卒倒した私は
初めてリアルに「すずめが死んでしまう!」
と思いました。
それがよりにもよって
深夜の出来事。
当然かかりつけの動物病院も
閉まっていたため、
必死で夜間診療をしている
動物病院を探しました。
どこを当たっても「鳥の専門医がいない」
と言われたのですが、
ある動物病院1軒だけが
診てくれると言ってくれたので
そこで飛び込みで緊急手術を
してもらうことになりました。
卵管脱で深夜の緊急手術に立ち会って

深夜に先生一人の対応だったため、
私が助手として手術に立ち会って
セキセイインコを保定せざるを得ませんでした。
あの時、自分の手の震えを抑えるのに
必死だったことをありありと思い出します。
私の手の中で処置をされるすずめを見ながら
…と強く思いました。
セキセイインコの発情抑制に食事制限を厳しく行うことを固く決意!

もう絶対にすずめを発情させない!
と心に誓った私は、
改めて今後について考えました。
そして今までやり方が甘かった食事制限を
より厳しくすることにしました。
方法としては、
朝と夕方に時間を決めて
餌をあげるというのはそのままに、
量を5グラムきっちりと
計量することにしました。
朝、シードを計ってケージに入れ、
ある程度食べたら餌箱を取り出し、
殻を取り除き、
残りを夕方に与えます。
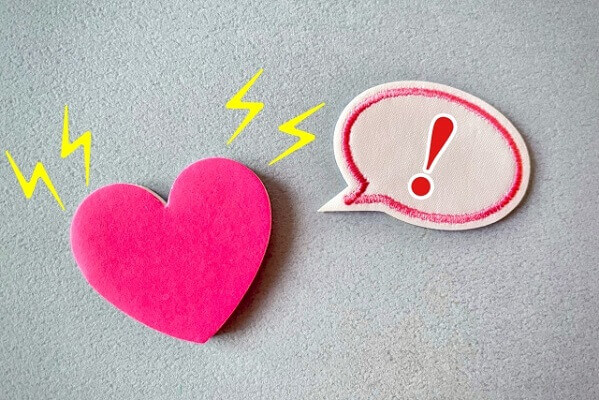
気の強いすずめは
厳しい食事制限に対して
大暴れして抗議していましたが、
私は心を鬼にして
この方針を徹底すると
決めていました。
するとほどなくして食事制限の効果が見え始め、
42gあった体重が36グラムまで落とせたのです。
持続的に血中カルシウム濃度が高値になるので体の負担が大きいです。ホルモン剤で早期に発情を止めることで、体の負担を軽減し、生殖器系疾患の予防になります。食事制限で常に飢えている様子があるようでしたら、使うと過剰な食欲が正常化して楽になることもあります。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 30, 2021

もともとが大柄なインコなので
平均体重まで落としただけでも
十分な発情抑制にはなったようです。
完全に発情抑制できているわけでは
ないのかもしれませんが、
その後は産卵の回数も個数も
明らかに激減しました。
愛鳥を守る「覚悟」に到達するまでに反省すべきこと

これまでの経験からの
私の反省点は3つあります。
夜間診療をしている病院を調べていなかったこと
「愛鳥の命を守る」覚悟が足りなかったこと
インコのように
身体の小さな生き物は、
本当にちょっとしたことでも
簡単に命を落としてしまうので
素早い判断と素早い対応が必要です。

すずめは体力があったので
頑張ってくれましたが、
あの時は命を落としていても
おかしくない状況でした。
卵管脱は脱出して時間がたって来院すると卵管脱は戻せても死亡する場合はあります。しかしいつから脱出したか正確にわからないのも実情です。
引用元:オダガワ動物病院
愛鳥の命を守る「覚悟」を決めなければ始まらない

緊急時に素早く動けるよう、
最低限でも動物病院の情報は
事前に持っていなければいけなかった
…と猛省しました。
「インコの命を守る覚悟が足りなかった」
…これが最も軽率だったことです。
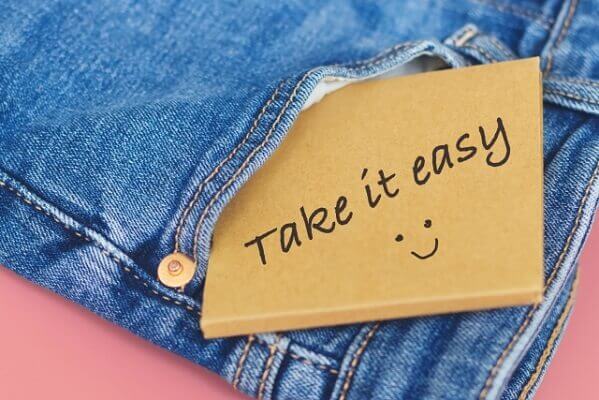
…とどこかで簡単に考えたいと
思い込んでいた甘さが、
自分の中にはあったのです。
人間だって一度の出産で
命を落とすことがあります。
それは鳥だって同じことで、
これをもっと真剣に
考えるべきでした。
毎日の体重測定を欠かさず適性体重のキープを目指す

これはインコを飼ったその日から、
当たり前にしていなければ
いけないことでした。
少しの変化に
気がつくためにも、
飼い主として
最低限の責任と義務です。
そういった意識が最初から私にもあれば、
すずめにあんなにつらい経験をさせずに
済んだのだと後悔しています。
やると決めた健康管理はきっちり継続する

愛情はたっぷりとそそぎながら、
長生きしてもらうための健康管理は
常に「厳しく」行う必要があります。
そう自覚させられた出来事でした。
今は愛鳥が少しでも長生きしてくれるように
強く願い続けながら
日々のお世話を楽しんでいます。