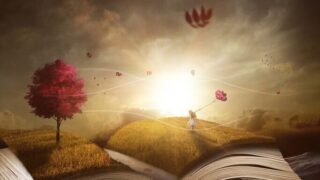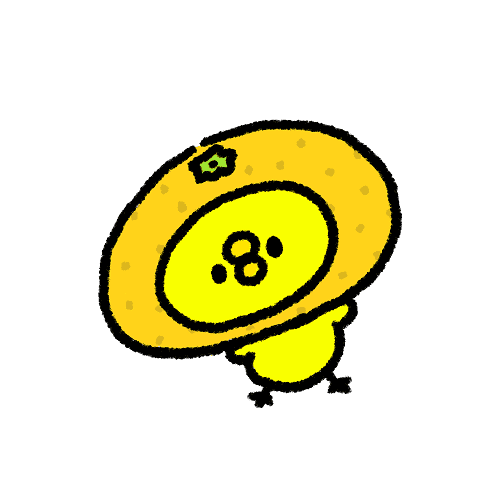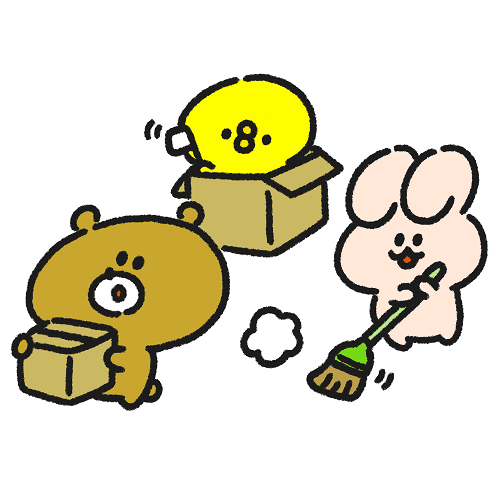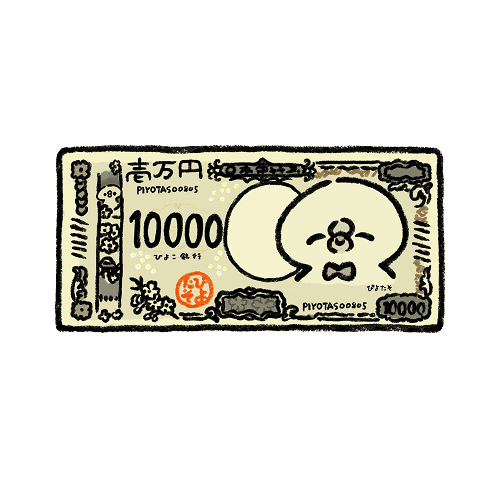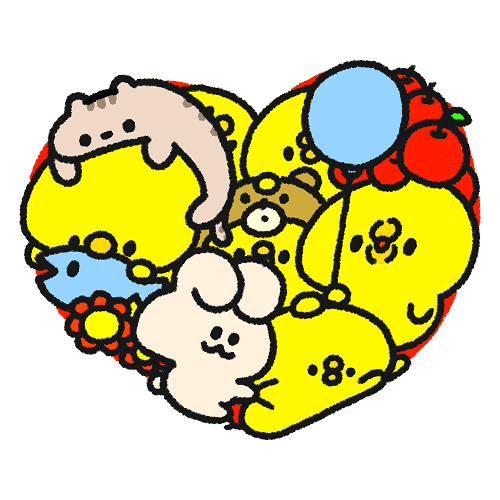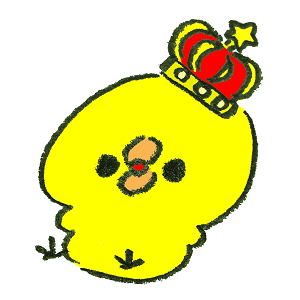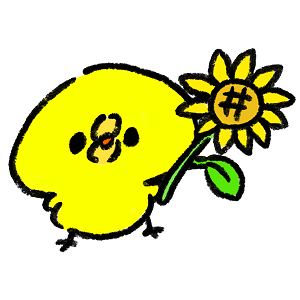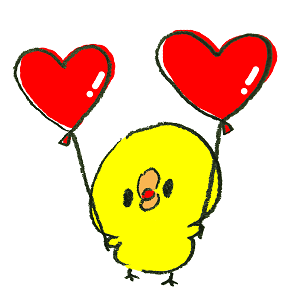インコの卵詰まりの見分け方・対処法・把握すべき4つのポイント
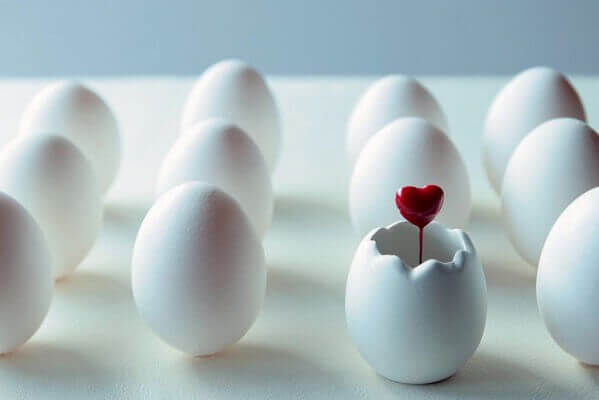
お腹に卵ができているのに
産み落とせず、
詰まってしまっている状況が
「卵詰まり」です。
微量栄養素の不足や
日光浴不足、
産卵を繰り返すことで体内に
カルシウムが不足することも
卵詰まりの原因であり、
卵詰まりは
秋から冬にかけて
多く起こります。
寒くなり始めは卵詰まりが増える時期です。産卵時は副交感神経が優位でないと産道が弛緩しません。寒いと交感神経が優位になるので産道が弛緩しにくくなります。しかし前もって保温すると発情しやすくなります。発情抑制には調子を崩さない程度の温度を保ち、卵ができてしまったら冷やさないが基本です
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 14, 2020
時間が経つほど発情が止まる可能性があり、待つほど産道が開かなくなります。Ca注射をして様子を見ようとする病院もありますが、Ca注射で産卵が促されるのはカルシウム不足の時だけです。また殻ができていないことが必ずしもCa不足ではありません。殻ができるまで数日様子を見てはいけません。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) December 9, 2022
卵管の機能障害があると血中Ca濃度が高くても卵殻形成に至らないことがあります。機能障害の原因の多くは不明ですが、血流障害や暑さによる過呼吸が考えられます。また卵殻膜まで形成された段階で停留し、卵殻腺まで降りて来ないと卵殻ができません。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) December 10, 2022
卵詰まりは症状が軽ければ
保温することで
無事産卵できることも
ありますが、
それでも産卵できない場合は
早めに病院に相談することを
おすすめします。
卵詰まりは死亡率が高いので
「もう少し様子を見よう」で
手遅れになることもありますから
注意が必要です。
インコの卵詰まりの症状は?

卵詰まりには、大きく分けて卵停滞と難産の2つがあります。卵管には子宮部と腟部があります。子宮部は卵殻を作る部分で、ここから卵が動かないのが卵停滞です。人で言う陣痛が起こらず卵が子宮部に停滞している状態です。卵停滞の場合は調子が悪くならず、すぐに気づかないことがあります。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 16, 2020
卵詰まりをしても必ずしも具合いが悪くなるとは限りません。長い期間卵管内に卵が停滞しカルシウムがついて変形していることがあります。この場合は手術でなければ治すことができません。雌は時折お腹を触って硬いものがないかどうかチェックしましょう。健康診断も大切です。https://t.co/7rLcgRZyMG
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 29, 2022
衰弱

インコは卵を産もうと
いきみ続けることで
体力が奪われ
衰弱します。
卵詰まりが初期のうちは
落ち着きなくケージの中を
動き回りますが、
ひどくなると
ケージの隅でうずくまり
動かなくなります。

卵詰まりを起こしたばかりのときは
元気そうに見えることがあって

飼い主が卵詰まりに
気づかないことも多いですが、
体内では状態が悪化していて、
突然ショック状態となったり
死亡する場合がありますので
卵詰まりは命に関わることが多く
あなどれません。
食欲不振と多飲

卵詰まりがひどくなると、
お腹の圧迫により
餌を食べなくなります。
水をよく飲むようになり、
嘔吐や下痢を
起こすことが多いです。
さらに衰弱すると、
何も摂取しなくなり
体重が激減します。
合併症
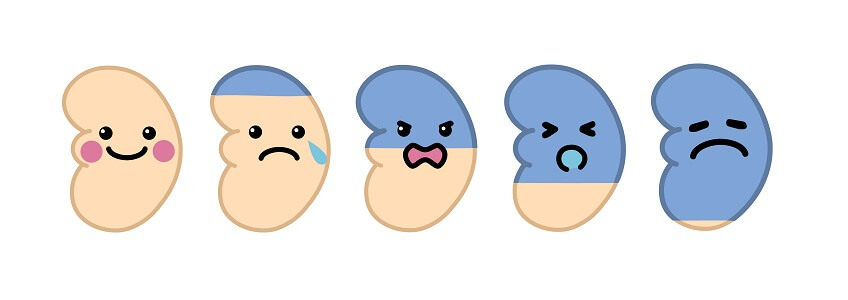
卵による内臓の圧迫や
生殖器官の異常などにより、
様々な合併症状が起こります。
肺や気嚢を圧迫…呼吸が荒くなる
生殖器官の異常…卵管炎、卵管蓄卵材症(卵管の中に卵となる物質がたまること)
尿が出ない…腎不全
インコの卵詰まりの見分け方

インコのお腹に卵があるかどうか触ってみる
インコを保定し、
お腹やお尻のあたりを触って
卵があるか確認します。
丸くて硬いものがあったら、
卵の可能性が高いですが、
軟卵の場合は
触ってもわかりません。
卵が出かかっている状態では、
インコのいきみに合わせて
総排泄孔から卵が
見えたり隠れたりします。

卵を確かめようと
インコのお腹を圧迫しすぎると、
内部で卵が割れて
卵管を傷つけてしまい
ショック死する可能性があるので
注意しましょう。
確実なのは保定してお腹を触ることです。上手く保定できない場合は、お腹の張りや急な体重の増加で判断します。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 15, 2020
インコのお腹が膨らんでいるか?
卵があるか触ってみても
判断できないときは、
インコのお腹やお尻、
羽が膨らんでいるか確認します。
個体によっては
もともと膨らんだ体型をしていて
卵があるかわからない場合があるので、
通常時のインコの体型を
よく観察しておきましょう。

普段から体重を計って
数字を把握しておくと、
体重が急増していた場合に
卵の重さだと判断できます。
インコがいきんでいるか?
インコがいきんで、
卵を産もうとする動作がみられます。
かがんでお尻を上げ、
羽を震わせたり
お尻を振ったりします。
いきむときに
声を上げることも多いです。

いきみすぎて腹圧がかかり
総排泄孔が腫れたり、
卵管などの生殖器が
総排泄孔から出てしまった場合は
すぐに動物病院へ連れていきましょう。

インコのフンや尿の異常はあるか?
水を多く飲むため
軟便、粘液便、
下痢を起こします。
インコ・オウム類、フィンチ類は盲腸を持たず大腸もほとんどありません。そのため哺乳類に比べて消化管が短く食物の通過速度が速いです。人のような便秘になることはほとんどなく、便が出ない時は腸閉塞や胃腸腫瘍、腹膜炎、排便神経・筋障害、卵詰まりや腫瘍などの物理的圧迫などによって起こります。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 2, 2021
卵詰まりで総排泄腔が圧迫されると排便ができなくなることがあります。鳥は腸の通過速度が速いため、排便できなくなると腸に便が詰まって膨らみ負荷がかかります。今回ブンチョウが2個卵が詰まって便が出なくなりましたが、緊急手術でことなきを得ました。便が全く出ない時は要注意です。 pic.twitter.com/n51gZsKbma
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 4, 2022
卵詰まりが重症化すると、
総排泄孔に卵が詰まって
いることが原因で、
フンや尿が
排泄できなくなることもあります。
インコの卵詰まりの対処法と病院で伝えるべき4つのポイント

卵詰まりが疑われたら、
自己判断で様子を見ずに
すぐ病院へ連れていきましょう。
すぐに動きが取れない場合は、
28~30℃の保温に努めます。
インコは体が小さく
体力の消耗が早いので、
最悪の場合その日のうちに
死んでしまうことがありますから、
できるだけ早く病院を
受診することをおすすめします。
そして卵は1日でできて産卵するものなので、様子を見ていいのは1日だけです。もし病院でそのうち産むから様子を見てといわれても、何日も様子を見ずにすぐにセカンドオピニオンを受けてください。https://t.co/cS5RtIoUOF
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 5, 2022
動物病院は
鳥の診療に長けた獣医のいる
動物病院を選んでください。
卵詰まりを起こしているインコは
慎重に扱わなければいけないうえ、
誤診や誤った治療法は
命にかかわります。

素人がオリーブ油を注入したり、
ひまし油を飲ませたりしても、
卵詰まりには全く効果がありません。
油を使うとインコの羽が汚れ、
体温の低下や毛引きの原因になるだけで、
ひとつもいいことはありません。
卵詰まりの時にオリーブ油を浣腸すると産卵するという情報がありますが効果はありません。産卵できないのは産道が緩んでいないからなので、油を浣腸しても卵管内に入って潤滑されることはありません。卵詰まりの時にお家でできることは保温です。病院に行くまでは足が温かくなるまで保温しましょう。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) October 16, 2020
動物病院へ連れていくときは、
寒い時間帯や時期は
しっかり保温をしておきましょう。

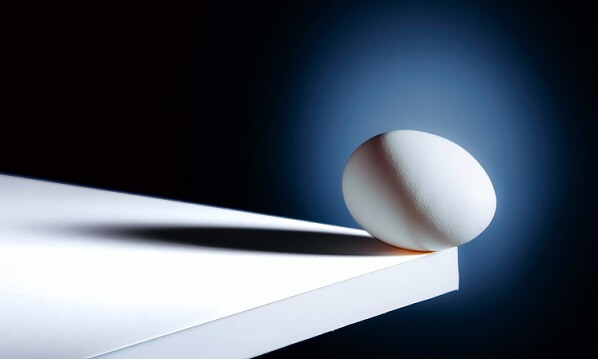
病院で診察を受ける際は、
以下のポイントを
獣医に伝えると
スムーズに診療が進みます。
インコの産卵経験について
初めての産卵か
過去の産卵で卵詰まりを起こしたことがあるか
インコが産卵中かどうか
お腹を触って卵を確認できている、総排泄孔から卵が見えている
いつ頃から産卵がはじまったか
直前まで他の卵を産んでいたか
インコの体の様子について
普段よりお腹や羽が膨らんでいるか
インコがいきんでいるか
インコの食欲と排泄の有無について
食欲はあるか、水を大量に飲んでいるか
フンや尿は出ているか