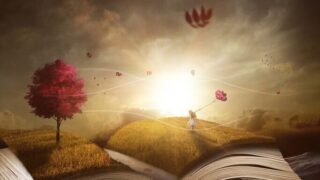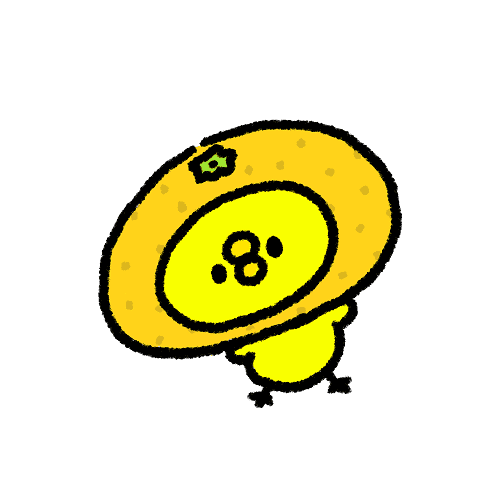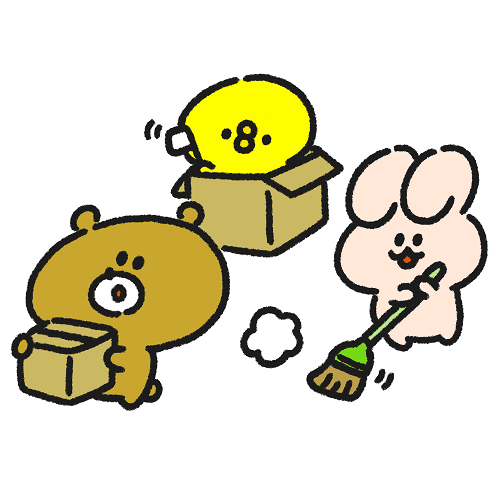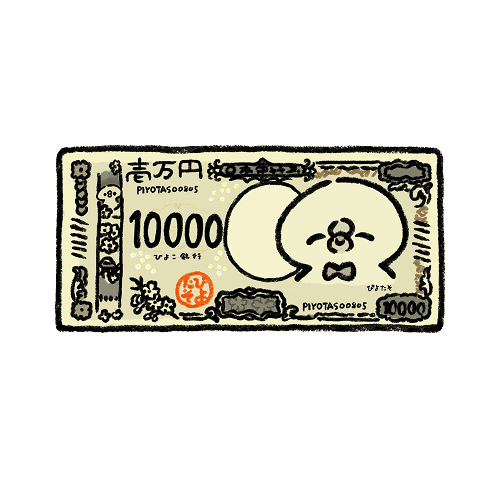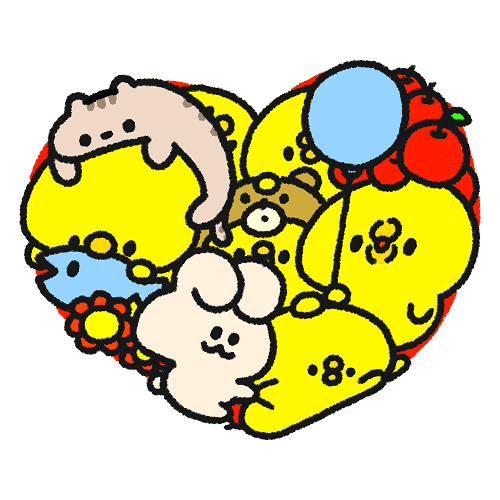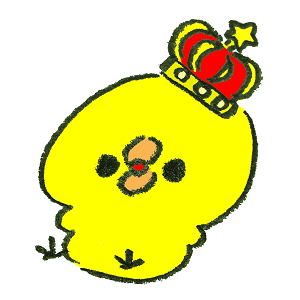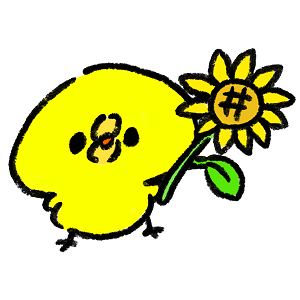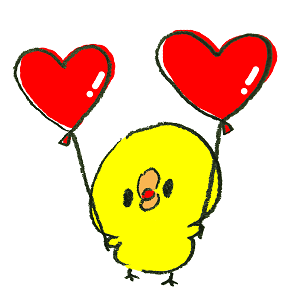インコに限らず、鳥類にはケガや病気を本能的に隠そうとする習性があります。
鳥自身がそれを隠そうとするのですから、病気のサインを早期に発見するのは意外と難しいです。
鳥の体は羽毛で覆われているので、体重が落ちて痩せてきても 見た目だけではなかなか気づきづらいものです。
インコの病気のサインとは?病気を隠す鳥の演技の見抜き方

皮膚に腫瘍ができていても
羽毛に隠れてしまって気づけないことが多く、
鳥が自分でその部分をつついてしまい、
出血して初めて腫瘍に気づいた
…なんてこともよくある話です。
インコの病気のサインに
早い段階で気づくにはどうしたらいいか?

いちばんカンタンな方法は、
人が鳥から気づかれない位置から
静かな環境で鳥をじっくり観察することです。
「鳥から気づかれない観察」がキモです。
インコの病気のサイン:ヒトが見ていない時の膨羽やうとうと

観察しているときに
インコが羽を膨らませていたり、
午睡以外で目を閉じて
うつらうつらしていたら
どこか体調がすぐれない可能性があります。
人の気配を感じた場合、
インコは羽を緊張させて
「いつもどおり」をよそおいます。
そのため体調不良の初期には
なかなか病気のサインを見抜くことが
難しいかもしれません。
逆に飼い主が見ているところで
羽を膨らませたり
頻繁なウトウトがある場合は、
病気がかなり進行していて、
気づいたときには手遅れ
…という可能性もゼロではありません。
インコの病気のサイン:餌を食べてるふり!砕いてるだけで食べていないことも

鳥は「名俳優」な生き物で、
餌を食べているフリまでします。
餌箱の中の餌をつついていても
確実に食べているとは限りません。
シードの皮をむいていても
食べているとは限りません。
種子の皮をむいて
砕いているだけのこともあるので、
意識的に観察を続けないと
初期の異変を見過ごしてしまうこともあります。
インコの病気のサイン:インコのフンと尿を見れば体調は見抜ける

名俳優なインコの演技に
飼い主さんは騙されてしまうことは
しばしばありますが、
どんなに演技派でも
飼い主を騙せないことがひとつあります。
それは排泄物…フンと尿の異常です。
ヒトと同じくインコも排泄物は
健康のバロメータで、
色・形・量・大きさ・水分量などを見れば
概ね健康状態の良し悪しの見当がつきます。
もし糞の量が少ないのであれば
餌を食べていませんから
食欲がない→食欲が落ちてる⇒体重は?
いつから食べていない?
…等の異変に気づきやすいでしょう。

また、糞や尿の色や水分量がおかしい場合は
細菌・真菌・寄生虫などの可能性もあるので、
早い段階で病院で検査をすれば、
大事に至らずにすみます。
フンが大きい・・・卵管炎
おしっこが黄色い・・・オウム病(クラミジア症) 肝炎
フンがお尻から垂れ下がっている・・・ジアルジア
下痢でフンが黒い・・・消化管内真菌症
血便・・・胃腸炎 中毒 消化管内異物(放鳥時などに鳥が異物を飲み込んだ)
緑色のフン・・・亜鉛中毒 ※青菜や着色料を食べて緑色になることもあります
フンの水分が多い・・・消化管内異物 そのう炎 卵詰まり 腹水 胃腸炎 肥満
多尿・・・痛風 ヘキサミタ 中毒 肝炎
食べた餌がそのまま排泄された・・・消化管内異物 消化管内真菌症
インコの病気のサイン:嘔吐!首を横に振るときにも要注意

フンや尿の異常はケージの掃除で
気づきやすいですが、
嘔吐がないかも確認してください。
フンきり網やトレイの敷き紙なども
意識してしっかりと観察することです。
ケージの下部ではなく
側面の金網もしっかり見てみてください。
金網に汚れや餌の粒子らしき固形物が
くっついていませんか?
そういうのがくっついていたとしたら
そのインコが嘔吐した可能性があります。

鳥は嘔吐するときに
首を横に振る習性があるので、
吐しゃ物が飛び散って
周囲にこびりつくことがよくあります。
下のトレイに吐しゃ物が落ちていなくても
周辺にそういう汚れがあれば
嘔吐が疑われます。
ケージ周辺の壁にもそういう痕跡がないか?
また 鳥自身の体が汚れていないか?
そこまで しっかりチェックしておきましょう。
インコの病気のサイン:体重減少や増加をチェック!定期的な体重測定を習慣づけて

定期的な体重測定は
インコの体調の異変にも気づきやすいので
体重をチェックする習慣をつけるとよいです。
オカメインコの場合は 強いストレスを受けただけでも数日で5~10グラム程度 体重が落ちてしまうことが普通にあります。
急に体重減少すると心配になりますが、
それが病気によるものかどうかは
飼い主さんがしっかり観察して
見極めるしかありません。
心配であれば、早めに小鳥の病院を受診すべきです。

短期間で体重が10~20%減少するのは
病気の可能性が高いです。
体重が3割減ってしまっていたら、
それはかなり危険な状態です。
オカメインコの体重は平均で90グラム程度ですから、
70グラムを切ってきたら
危ないと考えて間違いないです。
飼い主さんは日々入念なインコウォッチングを
習慣化しましょう。
その配慮が 愛鳥との楽しい時間を
長く共有することにつながります。