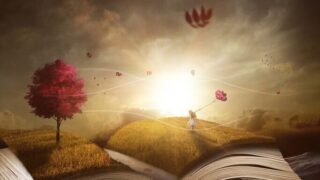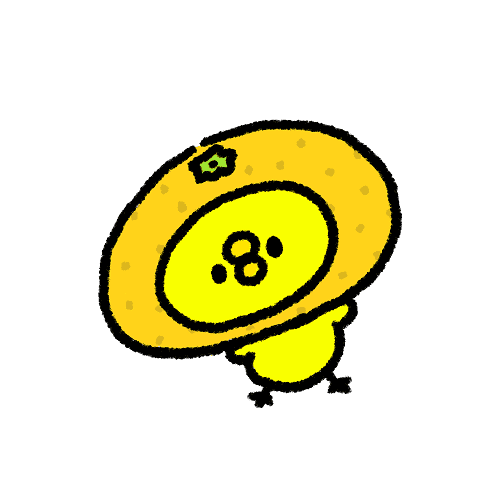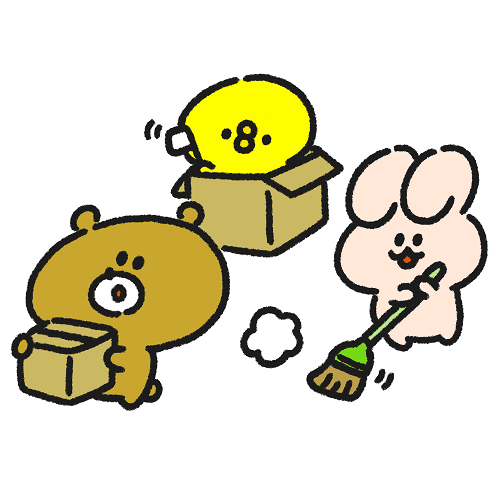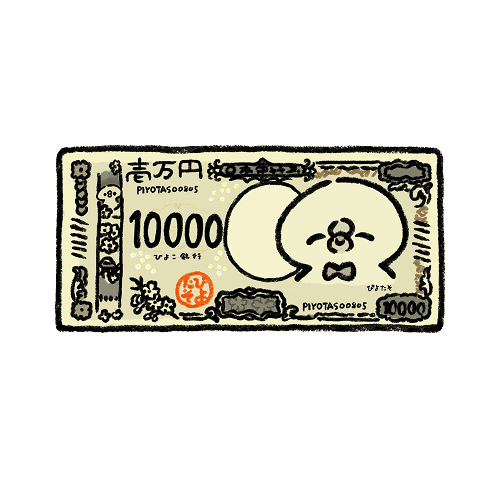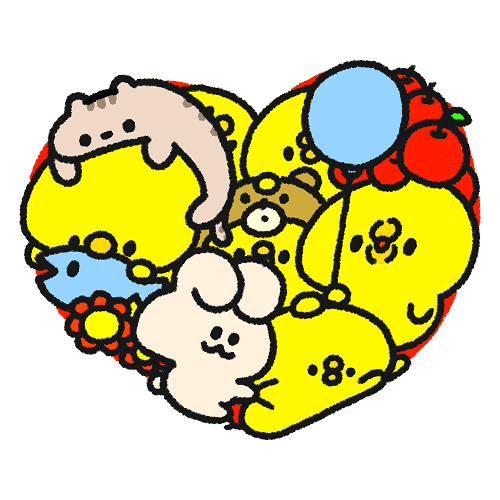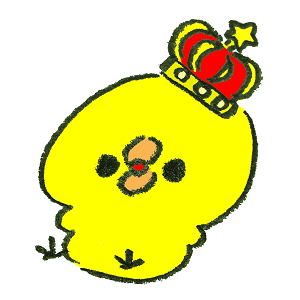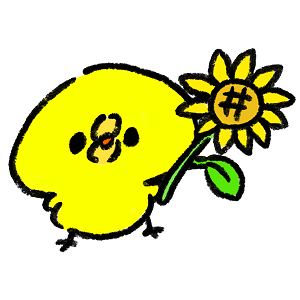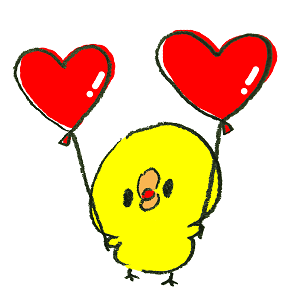インコの遊びはヒトが余暇を楽しむ遊びとはまったく違うもの。
インコの行動は本能や習性から来ているもの多いので、生活のすべてが遊びに通じています。
つまり人とは違って、インコは遊ぶことが生きることそのもの。
ここを履き違えていることがインコから嫌われた原因のひとつでもあります。
インコに嫌われたのは遊び方が悪いせい!ベタ慣れインコは作れる話①

…という人は、
インコの遊びを理解することから
始めてください。
べたなれまできっとあと一歩です。
フォージングトイを使って
一緒に遊ぶのも良し。
クリッカーを使って
簡単な芸を教えて
一緒に楽しんだり、
ボールを使ったヒトと鳥との
共同作業などもおすすめです。



…という方は
根本的にインコの特性や
飼い方を勘違いしています。
確かに一人遊びも必要なのですが、
はじめから一人遊びができるのは
かなり好奇心旺盛な一部のインコだけ。
ひとり遊びができるようになるためには
フォージングを取り入れたり
飼い主が遊び方を教えたりして
「共同作業」として関わる必要があります。
そうすることで次第に一人でも
楽しく遊べるようになっていきます。


ひとり遊びができるようになったら
遊び場を充実させてあげることも
おすすめですが、

初めから遊具をあずけるだけでは
インコが無関心のままです。
インコの関心を引いたり
遊び方を教えるのは
飼い主の重要な仕事のひとつです。
インコの「本能からくる遊び」は不用意に取り上げるべからず

インコの生活のすべてが
遊びに通じていますから
それが本能からくるものなのかを
まずは見極める必要があります。
生活と遊びがリンクしている「かじる」行為

インコの本能で
真っ先に挙げられるのが
「かじる」行為。
インコはかじることが大好きで
それが食べ物かどうかを
認識することも目的のひとつ。
シードや粟穂は
「おいしい」ももちろんですが
それをつついたり
かじったりすること自体が
楽しい遊びの一環です。

またインコのクチバシは
食べるために重要な部分なので、
常にお手入れを必要としますが、
そのお手入れのひとつが「かじる」行為。
かじることはクチバシの
のび過ぎを予防すること。
つまり生活と遊びがリンクしているので、
取り上げるわけにはいかない行為です。

インコがかじるのはいたずらではない

インコが物をかじることを嘆くヒトは多く
それを安易に「噛み癖」と呼ぶ人もいますが
「噛む」と「かじる」は似て非なるもので
「かじる」は癖でもいたずらではありません。
インコの本能を満たすために
必要な行為なので、
あまり目くじらを立てないでください。
(というかあらかじめ予防線を張るべし)
本能が満たされないと
欲求不満になります。
日常的に鳥は多かれ少なかれ何らかの欲求不満やストレスを感じています。これらを解消するには人や他の鳥とのコミニケーション、齧る対象物は自分ではなく木やおもちゃにすると言うのが健全な方法であり、それがエンリッチメントなのです。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 26, 2021
欲求不満を抱えて
イライラしているところで
さらに「かじる行為」を
頭ごなしに叱られては、
インコは立つ瀬がないばかりでなく、
ストレスが溜まって
メンタルが崩壊します。
手乗り崩れも必至です。

放鳥中にかじられて困るものを
片付けておくことはもちろん、
かじってOKなものを用意するなど
工夫を飼い主が凝らしましょう。
インコ・オウムはデストロイヤー!かじるの大好き破壊神はこわせるおもちゃが大好き
壁紙や柱などを
かじられないようにするためには、
そちらに注意が行かないように、
ほかに注意を向けさせる対策が必要です。

対策はそのお宅の住宅事情により
ケースバイケースですが
我が家のインコ部屋は
壁の一部にブルーシートを張ったり
エアコン周りに防風ネットを
使ったりしています。
インコの「巣作り行動の習性からくる遊び」をある程度は許容すべし

オカメインコを飼育している方なら、
狭いところや暗がりに分け入りたがるのを
何度か見かけているのではないでしょうか。
そしてそれが何を意味しているかも
想像はついていますよね?
そう「巣作り行動」です。
巣作り行動の習性は
インコの種によって様々ですが、
中には面白い行動をする鳥もいます。

たとえばコザクラインコの場合、
紙かじりが一種の巣作り行動です。
野生のコザクラインコは
細長く切り取った木の皮を
器用に腰に差して運んで
巣を作ります。
飼い鳥では木の皮がないので、
紙がその代用として使われます。
この行動は
生後3~4か月頃から始まるのですが、
成長するごとに巣材づくり行動に
磨きと拍車がかかっていきます。

それを見た飼い主の中には
…と思っている人もいるかもしれませんが、
いたずらだなんてとんでもない!
鳥たちはいつだって大まじめ。
生まれつき備わっている本能や
習性に従って行動しているだけの話です。
これでコザクラインコをたしなめても
言葉では到底鳥には通じませんし、
叱ったからといってなくなる行為でもない。
つまり叱ること自体が不毛な行為です。
このツイートのように 毛引きにでも走られたら大変なことになりますよね。
以前に紙を取りあげられたコザクラインコが自分の羽を抜いて齧り、それを自分の腰に刺すことを始めたことがありました。意識は自分ではなく、なるべく外に向かせることが退屈の対処であり毛引きの改善法です。それは人や鳥とのコミュニケーション、フォージング、チュワブルトーイ、紙などになります。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) November 1, 2021

そもそも言葉で叱って
わかる相手ではないので、
飼い主の方が愛鳥の特性を学んで、
その種に合った対策を
施すしかありません。
それが自然にできる人は
インコから好かれる飼い主。
そのように鳥の目線に立てる人は、
愛鳥から寄せられる信頼感も
厚いものになるはず。



インコをべた慣れにしたい人は、
まずはその部分に目を向けてみることを
おすすめします。
こちらに続きます