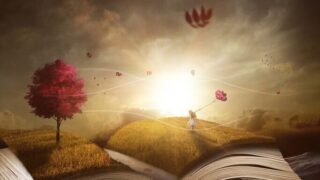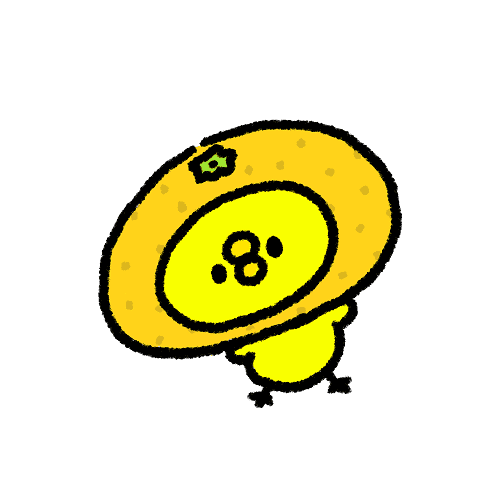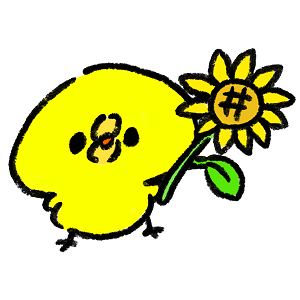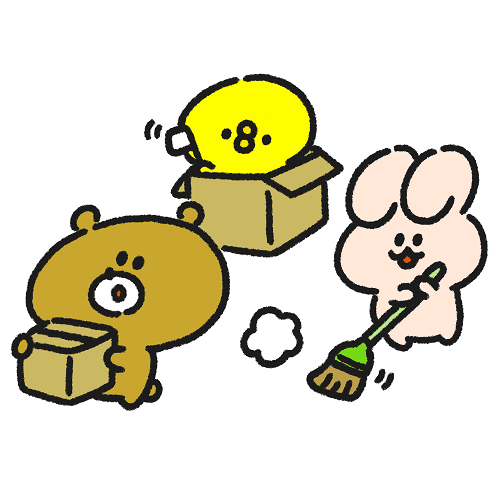インコの足裏が赤くなったり、一部が硬くなったりしていませんか?
もしかするとそれはインコがバンブルフット(趾瘤症)になっているのかもしれません。
バンブルフット(趾瘤症)は止まり木に接する部分で起こるので、こじらせてしまうと痛みが強くなったり感染症が起きたりと、鳥にとってとてもつらい状況です。
老鳥だけに起こるのかと思いきや、若い鳥にも頻発するので、予防することと早期発見を心に留めて 愛鳥の観察をする必要があります。
インコのバンブルフット!趾瘤症対策に止まり木保護テープのすすめ
餌箱の縁などにずっととまっていると趾瘤症になることがあります。この場合は餌箱の変更と共に止まり木も工夫をすると足の改善に役立ちます。ニームパーチは趾瘤症治療や予防の他、齧ることによるエンリッチメントにも繋がります。また既存の止まり木に保護テープを巻くのも趾瘤症改善に有効です。 pic.twitter.com/blJAMciKsF
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) February 13, 2021
インコの足裏が赤くなったり、
硬くなってタコができている状態を
バンブルフットといいます。
趾瘤症(しりゅうしょう)とも呼ばれる
インコに多い足の病気です。
バンブルフットとは?趾瘤症の原因は?自然治癒できる?
これは趾瘤症ですね。早く治療した方が良い状態です。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) March 18, 2021
原因は、肥満や腫瘍そして腹水による体重の増加、片方の足の障害、老化などによる握力の低下、太さや材質の合わない止まり木の使用など、足の裏に負担がかかるような条件が重なる事により発症します。
引用元:さつき台動物病院
バンブルフット(趾瘤症)の症状は、
初期は足の裏が
少し赤くなる程度ですが、
悪化すると足裏のタコが邪魔をして
止まり木をうまく
つかめなくなってきます。
さらに悪化すれば
インコが足を自由に
動かせなくなったり、
痛みも生じます。
バンブルフット(趾瘤症)は
一度治っても再発しやすく、
ひどい場合には
敗血症で死亡することもあります。
治療をせずに放置し、
止まり木などの足回りの環境を
ひとつも改善しなければ
自然治癒はまず無理です。
バンブルフットのオカメインコ(閲覧注意)
若くて健康なインコでも老鳥でもバンブルフット(趾瘤症)になる
こちらのボタンインコは定期的に通院していましたが、急に褥瘡ができていました。最近、高齢のせいか床敷の新聞紙に潜っていることが増えたとのことでした。脚力が弱り硬い床に踵を着いていると、すぐにこのような褥瘡ができることがあります。目立たない所なので、よく観察しましょう。 pic.twitter.com/CDmrihOH9M
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) July 17, 2022
健康でも褥瘡になる事があるんですね。大変勉強になりました。お忙しい中ありがとうございました。
— キュピたん (@inkonotomodachi) July 18, 2022
足の裏のことだけに
発見に時間がかかることが多く、
インコの動きに
変わった様子がなければ
なかなか飼い主は気づきません。
たまたまケージの側面に掴まった
インコの足の裏を見て驚いたり、
赤く腫れあがってから
はじめて気がつく飼い主も
少なくありません。
バンブルフット(趾瘤症)は
不適切な止まり木の使用による
足裏への負担や血行不足など、
さまざまな理由が原因で発症します。
踵の褥瘡は床について体重を支えていることなので、止まり木が太いか、硬い平らな所にいることが多いです。また肥満で体重が重かったり、何らかの原因で握力が弱くても、踵から跗蹠に褥瘡ができる原因となります。
治療法は、そのようになります。— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) July 18, 2022
インコの足のタコや褥瘡…かたい床や肥満がバンブルフット(趾瘤症)を招く

止まり木だけでなく、
硬い床での生活や
体重増加も
バンブルフット(趾瘤症)の原因です。
足にできたタコや
褥瘡(床ずれ)のようなものですから
インコの足裏だけでなく
踵にもこれらの症状が現れます。
うちは踵の部分にタコがあります。おデブちゃんだったので体重の蓄積で足に負荷がかかっていたのでしょう。体調を崩したと同時期に左脚が不自由になって右脚で移動するようになり、タコが悪化しています。これ以上悪くなると血が出て穴が空く→菌が入る→腐る→切断と言われました(꒦໊ྀʚ꒦໊ི )
— yukkachan☻ (@638Sang) March 23, 2021
生活環境を改善することはもちろん、
体重の管理にも気を配る必要があります。
趾に障害が出て止まり木にとまれなくなり床で生活していると、当たっている部分が赤くなったり趾瘤症になったりすることがあります。この場合の対策は太ってるなら食事制限をして体重を正常に戻すことと床を柔らかくすることです。柔らかくするにはタオルの上にリードクッキングペーパーがお勧めです。 pic.twitter.com/jrmETanOt9
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) April 28, 2022
体重増加は単なる肥満だけでなく、
腫瘍や腹水による場合もあります。
足に現れた障害を甘く見ないで、
動物病院に相談することが賢明です。
インコのバンブルフット対策!止まり木に保護テープを巻くだけでも予防につながる
ななちゃん足痛い動きにくい以外は元気そうにしてる
腎臓病や通風だったらもっと辛そうにするらしい
足の感じと原因に思い当たることが多いので趾瘤症の可能性が高い?
明日病院行くか pic.twitter.com/CsNP7r6Wvg— 艶子 (@glosshope43) July 26, 2022
止まり木に保護テープを
巻いてあげる方法が
バンブルフット(趾瘤症)の
予防や改善のために
簡単にすぐにできる対策です。
バンブルフット(趾瘤症)は
早期発見・早期治療で
改善が見込める疾患ですので、
止まり木の改善と、
日頃から足を含めた全身のチェックを
こまめにすることが大切です。
バンブルフット(趾瘤症)かも?
と気になったときには、
まずは一度獣医さんに
相談することをおすすめします。
止まり木に巻くおすすめの保護テープは?
適切でない場所に止まっている子に起きる足のトラブルを「趾瘤症(バンブルフット)」と言いますが、コレは5年とか10年続いた結果、起きる病気なので、焦らないで環境を改善してして下さい
また、この病気は自然界には存在しないと言われていて、特殊な環境で暮らす飼鳥の病気と言われているそうです
— いいちこインコの飼い主@花沢りん吉 (@iichiko_hana) July 13, 2020
凹凸のないつるつるした
止まり木に止まっているインコは、
人間が硬い板の上で
正座しているようなものです。
そう考えるとつらいですよね。
早急にインコの足のために
クッションをつけてあげたいものです。
人間でいうところの座布団が、
インコにとっての
止まり木に巻く保護テープなのです。

インコは太すぎる止まり木は
うまく掴めませんし、
ボリュームがあるものをまくと
中身をつついて出したり、
誤飲する恐れがありますので、
薄い保護テープを巻いてあげるのが
おすすめです。
止まり木に巻く保護テープは
自着生テープを使います。

止まり木の保護テープは
人間が使うテーピングでも代用可能ですが、
医療用に作られているものの中には
湿布薬のようなニオイが
するものもあります。
この独特なニオイが
鳥体にどんな影響を与えるか
わかりません。
人間用の鎮痛効果のある湿布に
使われているサリチル酸メチル…
これは揮発性で
「鳥に有害である説」がありますので、
自着テープならどれでもいいと
考えない方がいいです。
過去にアロマディフューザーが原因で
オカメインコが亡くなった事故も起きていますので、

小さな小鳥に使うものは
神経質すぎるくらいでちょうどいいです。
婆ちゃんちの通院してるインコがバンブルフットにもなってしまい、止まり木に巻く包帯をこれから探しに行く。止まり木に巻いてふかふかにしてあげると良いらしい。100均にも売ってますよ、と言われたけど、婆ちゃんちの近くの100均で売ってたのはアロマ配合だったのでインコに毒・・・
— よ氏 (@sakuraRITZ) July 10, 2021
飼い主にもはっきりとわかるニオイは
インコにとって刺激が強すぎたり、
場合によっては命の危険にも及びます。
よって止まり木用に販売されている
保護テープを使用するのが安全です。
止まり木の保護テープの巻き方のコツ
ハナちゃんとリリですが、実は先日、お医者さんに行った時、足にタコがあることがわかりました。そこで、今日止まり木にテープを巻いたんですが、
予想通りというか、拒否反応が凄いです。全く困ったもんです。 pic.twitter.com/Pgq1BMBn59
— tosiya21 (@tosiya21) September 7, 2021
自着性の保護テープは
止まり木にくるくる巻いていくだけなので
使い方が難しいことはないのですが、
巻き方にコツがあります。
一か所に巻く量を一定にしない。
この巻き方は
バンブルフット(趾瘤症)の予防効果が
期待できます。
自然木の止まり木は
所々がごつごつしていて
太さが一定ではないように、

保護テープを巻くときにも
厚みに変化をつけてみるのがいいです。
保護テープを多めに巻つけるところ、
少なくするところ
…というように変化をつけると、
さらにインコの足への負担を軽減できます。
多めに巻くといっても
何重にも巻くと太くなりすぎて
インコがつかめなくなってしまうので
二重もしくは三重程度で大丈夫です。

多少の余裕を持たせながら巻いていく
保護テープはよく伸びる特徴がありますが、
引っ張りながら強く巻きつけると
クッション性は減ってしまいます。
保護テープの効果を十分に発揮するためには
ほんの少しだけゆるく
余裕を持たせながら巻くのがおすすめです。
巻き方は良いように見えますが、オカメインコには少し太いように見えます。合うかどうかは鳥さんがとまりやすそうか見てみてください。ステージはずっととまるようでしてら無くても良いものですが、テープ巻くのでしたら丸ごと巻くと良いでしょう。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) January 27, 2021
ありがとうございます。
赤丸が変形した指、黄色丸が赤い場所です。
早急に対策します。 pic.twitter.com/i1bggX4Pj6— atsu@鳥(ピース16歳🐥) (@atsuPeacepiece) January 29, 2021
保護テープを巻いた止まり木に慣れるまで時間をかけて歩み寄る

少しずつインコに保護テープに馴らすことから始めていく
インコのなかには
保護テープを巻いた止まり木を
拒絶する個体も少なくありません。
ビビりが多いオカメインコなどは、
保護テープを巻いた止まり木に
慣れるまで少し時間がかかる子もいます。
保護テープを巻いた止まり木を
見せて歩み寄りながら、
時間をかけて少しずつ
慣れてもらいましょう。
怖がるようであれば、まずはケージの外に置いて見慣れることから始めると良いと思います。テープは止まり木の端に少しだけ巻いたりして見慣れさせて徐々に増やしていってみて下さい。
— 海老沢和荘 (@kazuebisawa) March 22, 2021
インコの抵抗感を少なくさせるためには、
以下の2つの対策が有効です。
止まり木の一部だけに保護テープを巻く
警戒心の強いインコには
新しいものを使用する前に
それをインコの視界に入るようにしておくと
「あれは怖いものではないのだ」と理解して、
受け入れるのも早くなるでしょう。
保護テープの色選びのコツ
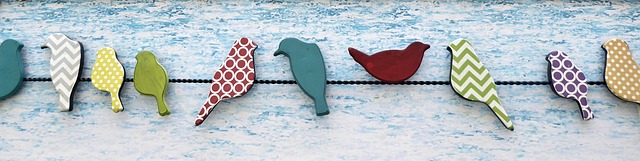
保護テープの色はブラウン系、
ホワイト系と
いくつか種類はあります。
もともと使っていた止まり木に近い
ナチュラルな色のほうが
インコの抵抗感は少ないのですが…
すでにバンブルフット(趾瘤症)になって
足に傷があるインコには
汚れや出血などがすぐにわかるように
薄い色合いの保護テープの方が
異変に気付きやすいかもしれません。
保護テープの保管の注意
一度に全量の保護テープを
使用しない場合、
使い残しの保護テープは
水に濡れない
湿度の低い場所
…で保管しましょう。
保護テープの多くは
使用前に湿ると
粘着力が落ちてしまいます。
また、保護テープは直射日光が当たったり、
高温になる場所には置かないでください。
熱で保護テープが変色したり
接着面がベトベトにくっつく恐れがあります。
止まり木や保護テープを清潔に使うための工夫
凛の通院が無事に今回で終わりました。タコは少し残るものの、炎症や腫れはなくなっていて、足の力も戻ったとのことです。約1ヶ月頑張ってお薬飲んだね。偉かったよ~。止まり木の包帯テープやケージ床のタオルとペーパータオルは常時やることになりました。#オカメインコ#長男#通院 pic.twitter.com/xR2aafWIqc
— Jun 酉年生まれ (@junmao0723) June 6, 2021
バンブルフット(趾瘤症)では
足裏が負傷しているケースが多いです。
糞や汚れが傷口について
菌が体内に侵入しないように
気を配る必要があります。
保護テープを巻いたあとの止まり木は
水洗いできないので、
巻く前に止まり木を消毒して
きれいな状態にしておきますが、
止まり木の予備を用意しておけば、
いつもきれいな状態をキープできます。

止まり木の保護テープの巻き換えの頻度は、
衛生面を考えると
週に1度がおすすめです。
バンブルフット(趾瘤症)は発症例が多くて
再発しやすい病気ですので、
発症を未然に防ぐために
今から止まり木に保護テープを巻く
予防対策を講じておくことが大切です。
.
最年長のセキセイがカルシウム沈着で趾関節の固着+軽度のバンブルフットです。 今はまだパーチを握ることはできますが、いつ握れなくのかも分からないのでいつかのためにオーダーいたしました。
プラスチック製のブランコが大好きで長時間乗っているせいか 通院時に足の裏が赤く擦れていたのでこちらで購入し 止まり木とブランコに巻きましたら治りました。
引用元:Yahoo!ショッピング
インコの止まり木は自然木がおすすめ!つるつるすべすべの止まり木は足にやさしくない!

「バンブルフット(趾瘤症)」は、自然界では見る事のない、飼鳥特有の病気のようです。
真っ直ぐな止まり木は、鳥にとって、何一つ、良い事はありません。真っ直ぐな止まり木が「鳥カゴの初期セット」なのは、大問題で、飼鳥のグッズも、まだまだ、信頼出来ないモノが沢山ある事を知って置いて下さい。 https://t.co/XW1OX8Vwkp
— いいちこインコの飼い主@花沢りん吉 (@iichiko_hana) October 12, 2018
多くの方が使っている止まり木は、
元々ケージに付属してくる
表面がつるつるとした
凹凸のない
シンプルな止まり木ではないでしょうか。
そういう止まり木は一見すると
足にやさしそうに見えますが、
実は鳥の足への負担が大きく、
凹凸がない分
滑りやすくなっています。
このような止まり木では
インコは止まり木から落下しないように!と
余計な力を足に入れることになり、
それがバンブルフット(趾瘤症)に
つながることもあります。
いいちこインコさんも、足のトラブルの原因となる「真っ直ぐな止まり木」は避け「自然木の止まり木」を使うなどして足裏の対策をしていましたが、加齢により免疫力が落ち、小さな足の傷口から入った雑菌によって炎症が起きるようになってしまいました。
愛鳥家の皆さん!足裏対策は大事ですよ! pic.twitter.com/4vJFWYZi5E
— いいちこインコの飼い主@花沢りん吉 (@iichiko_hana) December 22, 2020
あまり止まり木から動かないインコや老鳥は
つるつるの止まり木では
足の血行不足にもなりやすく、
バンブルフット(趾瘤症)のリスクが高まります。
足が悪くなったり
止まり木に止まれなくなる原因は
いろいろありますが、
鳥も年齢と共に筋肉量が低下するので、
今まで使っていた止まり木からでも
落ちてしまうようになる個体が多いのです。
老鳥インコだけでなく
若い鳥にも多く発症するバンブルフット(趾瘤症)を
予防するためには、
止まり木に工夫をすることが有効です。